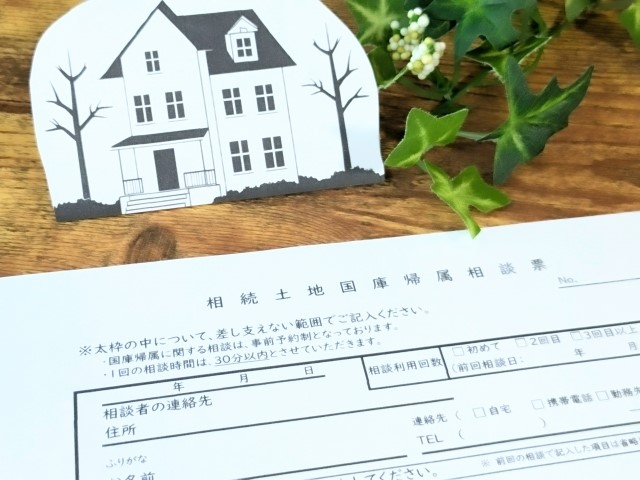遺言書を作成すると、「財産のすべてを○○に相続させる」といった内容を自由に定めることができます。
しかし、相続には「遺留分(いりゅうぶん)」という、法律で最低限保証された取り分が存在します。
この遺留分を無視してしまうと、遺された家族との間でトラブルに発展することも少なくありません。
本記事では、「遺留分とは何か」「遺留分を侵害された場合どうすればいいのか」について、行政書士がわかりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、一定の相続人に認められる「最低限の取り分」です。
たとえ遺言書で「全財産を長男にあげる」と書かれていても、他の相続人は一定割合を請求できる権利があります。
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人)
- 直系尊属(父母など)
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合はどのくらい?
遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 相続財産の1/2 | 配偶者1/4、子全体で1/4 |
| 配偶者のみ | 相続財産の1/2 | 配偶者1/2 |
| 子のみ | 相続財産の1/2 | 子全体で1/2 |
| 父母のみ(直系尊属) | 相続財産の1/3 | 父母全体で1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし | ― |
たとえば、相続財産が2,000万円で、妻と子1人が相続人の場合、遺留分は全体で1,000万円。
そのうち妻500万円、子500万円がそれぞれの最低保証額となります。
遺留分侵害額請求とは?
もし遺言や生前贈与によって、ある相続人の遺留分が侵害されている場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この請求は、かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年の民法改正により、金銭請求権として整理されました。
つまり、現在では「遺産そのもの」を取り戻すのではなく、「侵害された分に相当する金額」を請求する形に変わっています。
遺留分侵害額請求の手続きの流れ
遺留分侵害額請求を行うには、次のような手順を踏みます。
① 遺留分の計算
まず、相続財産の総額を確定します。
現金や不動産だけでなく、被相続人が生前に行った贈与(特に相続人への贈与)は、一定の期間内であれば「持ち戻し」として考慮されます。
② 相手方への通知
侵害されている相手(財産を多くもらった相続人など)に対し、内容証明郵便などで請求の意思を伝えます。
この通知が時効を止める重要な手続きにもなります。
③ 協議・交渉
請求を受けた相手と、金額や支払い方法について協議します。
多くの場合、交渉で合意すれば「遺留分侵害額請求に関する和解書」を作成して解決します。
④ 裁判による解決
協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
それでも決着がつかない場合、最終的には「訴訟」によって金額を確定します。
請求の期限に注意!
遺留分侵害額請求には時効があります。
民法第1048条によれば、
- 「相続の開始および侵害を知ったときから1年」
- 「相続開始から10年」
のいずれか早い方が経過すると、請求できなくなります。
つまり、「遺言書の内容を知ってから1年以内」に行動しないと、権利が消えてしまうおそれがあります。
請求を検討している方は、なるべく早く専門家に相談することが重要です。
実際によくあるトラブル事例
事例1:父の遺言で全財産を長男に…
父が亡くなり、「全財産を長男に相続させる」との遺言書が見つかりました。
二男は納得できず、遺留分を計算したところ、父の遺産3,000万円に対して1/4(750万円)が遺留分にあたると判明。
二男は内容証明で長男に請求し、最終的に600万円の支払いで合意しました。
事例2:生前贈与で不公平に…
母が生前に長女へ2,000万円の生前贈与をしていたケース。
相続財産が1,000万円しか残っていなかったため、他の相続人が遺留分を侵害されたと主張。
生前贈与も考慮して再計算した結果、長女から金銭を支払うことで和解しました。
このように、生前贈与も遺留分の対象になる場合があるため、注意が必要です。
遺留分トラブルを防ぐためには?
相続トラブルの多くは、「遺言書の内容が一部の相続人に偏っている」ことから発生します。
被相続人としては、「自分の意思を尊重してほしい」と思う一方で、残された家族が争うのは本意ではないはずです。
トラブルを防ぐためには、
- 遺留分を考慮したバランスの取れた遺言書を作成すること
- 理由を付記した「付言事項」で家族への思いを残すこと
が有効です。
また、遺留分の計算や文面の書き方には法律的な知識が必要なため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:遺留分を理解して「争族」を防ぐ
遺言書があっても、遺留分を侵害すると相続トラブルの火種になります。
一方、遺留分侵害額請求は金銭での解決が基本となり、比較的スムーズに処理できるようになりました。
被相続人にとっては「家族が争わない遺言書」を、
相続人にとっては「自分の権利を正しく守る知識」を持つことが大切です。