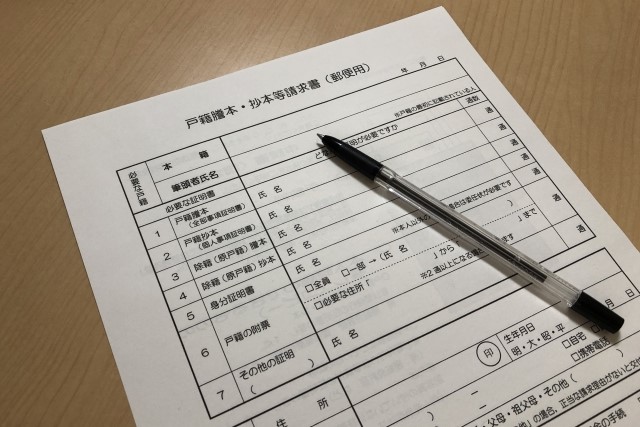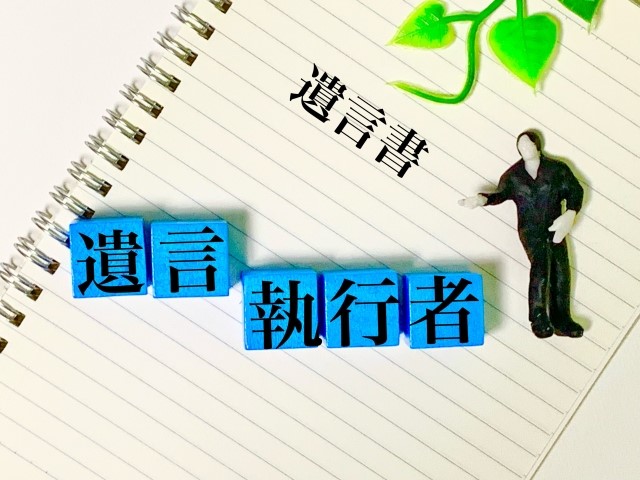成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を支援するための制度です。しかし、実際に運用される中でさまざまな課題が指摘されており、利用をためらうケースも少なくありません。本記事では、成年後見制度の限界とその背景について解説し、今後の改善策についても考えていきます。
1. 成年後見制度とは?
成年後見制度は、大きく分けて 「法定後見」 と 「任意後見」 の二種類があります。
- 法定後見(後見・保佐・補助)
家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産管理や契約行為をサポートします。判断能力の低下の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれています。 - 任意後見
本人が判断能力を失う前に、自分で信頼できる後見人を決めておく制度です。
この制度の目的は、判断能力が低下した人の権利を守りながら、日常生活をサポートすることですが、実際の運用ではいくつかの問題点が浮かび上がっています。
2. 成年後見制度の課題
① 申立ての負担が大きい
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、医師の診断書を提出し、審理を経て後見人が選任される必要があります。この手続きには数か月を要し、手間や費用がかかるため、利用をためらう人も多いのが実情です。
② 費用負担の問題
法定後見制度では、後見人の報酬が発生します。特に弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職後見人が選任されると、月額2~5万円程度の報酬がかかることもあります。財産が少ない人にとって、この金額は大きな負担となります。
③ 家族が後見人になりにくい
かつては家族が後見人となるケースが一般的でしたが、近年では裁判所が専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士など)を選任する傾向が強まっています。これにより、家族が本人の財産を管理しにくくなり、また家族の意向と専門職後見人の判断が食い違うこともあります。
④ 本人の自由が制限される
成年後見制度を利用すると、本人の財産管理は後見人が行うため、本人が自由に預貯金を引き出したり、大きな買い物をしたりすることができなくなります。また、後見が開始されると、遺言を作成できなくなるといった法的な制約もあります。
⑤ 後見人の不正やトラブル
後見人の中には、不適切な財産管理を行ったり、報酬目的で不当に長く後見を続けたりするケースも報告されています。こうした不正を防ぐため、家庭裁判所による監督がありますが、すべてのケースを十分にチェックするのは難しいのが現状です。
⑥ 途中で辞められない
成年後見制度は一度開始されると、原則として本人が亡くなるまで続きます。途中で本人の判断能力が改善したとしても、簡単に後見を終了することはできません。そのため、柔軟な対応が求められますが、現行制度ではこの点が十分に考慮されていません。
3. 成年後見制度の改善に向けて
こうした課題を解決するために、以下のような改善策が考えられます。
◎ 任意後見制度の普及促進
任意後見制度を活用すれば、自分で信頼できる後見人を決められるため、制度の使い勝手が向上します。ただし、現状では利用者が少ないため、制度の周知と利用促進が必要です。
◎ 費用の負担軽減
成年後見制度を利用しやすくするため、後見人報酬の助成制度を充実させたり、低所得者向けの支援策を強化したりすることが求められます。
◎ 家族後見の柔軟な運用
家族が後見人になれるよう、裁判所の運用を見直し、家族による後見をもう少し柔軟に認めることも重要です。
◎ 成年後見の段階的な見直し
現在の制度では、判断能力が一度「不十分」と認定されると、改善しても後見が続きます。段階的に解除できる仕組みを作ることで、本人の生活の質を向上させることができます。
4. まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した人を保護する重要な仕組みですが、申立ての負担や費用、本人の自由の制限、後見人の不正などの問題があることも事実です。今後、より柔軟で利用しやすい制度へと改善することが求められています。
後見制度の利用を検討している方は、制度のメリットとデメリットをよく理解し、自分や家族にとって最適な方法を選ぶことが大切です。行政書士や弁護士などの専門家に相談しながら、最善の選択をしましょう。