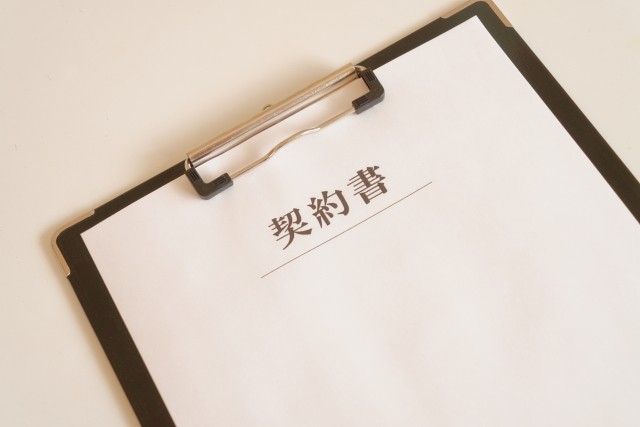「親の土地に家を建てても大丈夫?」「名義はどうすればいいの?」
このようなご相談は、相続や不動産の手続きの中でも非常に多く寄せられるテーマです。
親の土地に子どもが家を建てる場合、土地の所有権は親のままで、子が無償で借りて使う形になります。この関係は法律上「使用貸借(しようたいしゃく)」と呼ばれます。
本記事では、使用貸借の基本的な仕組みから、相続や売却の際に起こりやすいトラブルまで、分かりやすく解説します。
使用貸借とは?その基本的な意味
使用貸借とは、無償で物を借りて使用し、返す契約のことをいいます(民法593条)。
つまり、「お金を払わずに使わせてもらう」契約です。
たとえば、親が子に「うちの土地に家を建ててもいいよ」と言う場合、そこに金銭の授受がないときは使用貸借になります。
使用貸借のポイント
- 使用する目的が明確である(例:住宅建築のため)
- 期限の定めがないことが多い
- 無償である(賃貸借契約との最大の違い)
これに対し、賃貸借契約は賃料(家賃)を支払う契約であり、借地借家法の保護を受けることができますが、使用貸借にはその保護が及びません。
親の土地に家を建てるときの法的関係
親の土地に子が家を建てると、土地と建物の所有者が異なる「土地建物の分離所有」状態になります。
この場合、建物を建てるための土地利用権が必要ですが、親子間では次の2パターンが考えられます。
賃貸借契約
- 子が親に地代を払う
- 借地借家法の適用があるため、子の権利が強い
- 相続や売却があっても、借地権として存続する
使用貸借契約
- 地代は払わず無償で借りる
- 借地借家法の適用がなく、親(貸主)の権利が強い
- 親が亡くなると契約終了になる場合がある
一般的には、親子間ではお金のやり取りをしないため、使用貸借として扱われることが多いです。
親の土地に家を建てた場合のリスク
親の好意で土地を貸してもらうのは良いことですが、後々のトラブルの原因になりやすい点に注意が必要です。
親が亡くなった後の相続トラブル
親が亡くなって土地を相続する際、他の相続人(兄弟姉妹など)との間で不公平感が生じることがあります。
「長男は親の土地に家を建てて住んでいるのに、地代も払っていない」
このような不満が相続時に噴出し、遺産分割協議が難航するケースは少なくありません。
土地を返還しなければならない可能性
使用貸借では、貸主が「目的が終わった」と判断すれば、返還請求が可能です。
たとえば、
- 親が亡くなって相続人が土地を相続した
- 相続人が「土地を売りたい」と主張した
といった場合、建物を取り壊して返還を求められることがあります。
つまり、子の居住権が不安定という点が最大のリスクです。
住宅ローンが通りにくい
土地が自分の所有でない場合、金融機関は担保設定ができないため、住宅ローン審査が厳しくなります。
親子間で使用貸借契約書を作成しても、借地権のような法的強制力は弱く、ローン審査では不利に働くことが多いです。
トラブルを防ぐための対策
親の土地に家を建てる場合、将来の相続まで見据えた準備が重要です。
書面で契約内容を明確にしておく
口約束のままだと、後に「貸した」「借りた」で争いになりかねません。
親子間でも、使用貸借契約書や覚書を交わしておくことが望ましいです。
契約書には次のような内容を盛り込みます。
- 使用目的(住宅用であること)
- 返還の時期や条件
- 相続が発生したときの扱い
将来の相続を踏まえた遺言書の作成
親が「この土地は長男に使わせ続けたい」と思っている場合は、遺言書で意思を残すことが大切です。
使用貸借では相続とともに契約が終了する可能性がありますが、遺言によって土地の所有権を長男に相続させれば、居住の安定が図れます。
地代を設定して借地契約にする
親子間でも、少額でも地代を支払うことで賃貸借契約として扱われる可能性があります。
借地借家法の適用を受ければ、居住権がより強く保護されます。
ただし、税務上は親から子への贈与とみなされる場合もあるため、専門家への相談が必要です。
建物登記と土地の名義を整理しておく
建物は子名義、土地は親名義という状態では、将来的に名義の不一致が問題になることがあります。
将来、親が亡くなった際の相続登記や売却の手間を減らすためにも、事前に登記簿や固定資産税の名義確認をしておきましょう。
税務上の注意点
使用貸借は無償利用であるため、原則として贈与税の対象にはなりません。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
- 土地の所有者が法人の場合:法人が個人に無償で貸すと「使用料相当額」を役員給与として課税される可能性があります。
- 建物が子名義で建てられた場合:親が土地の使用を無償で許可することにより、土地使用権の贈与と見なされるケースもあります。
税務判断はケースごとに異なるため、税理士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
親の土地に家を建てることは珍しくありませんが、法律上は使用貸借関係になることが多く、安易に進めると将来的なトラブルに発展するおそれがあります。
- 使用貸借は無償利用の契約であり、借地借家法の保護がない
- 親の死後、土地の相続人が返還を求めることができる
- 相続や贈与税の問題も関わる
こうしたリスクを避けるには、
①契約内容を明確にする、
②遺言書を用意する、
③専門家に相談する、
この3点が大切です。
| 項目 | 使用貸借 | 賃貸借 |
|---|---|---|
| 対価(地代) | 無償 | 有償 |
| 契約の安定性 | 弱い | 強い(借地借家法の保護あり) |
| 親の死後 | 契約終了の可能性 | 原則として継続 |
| 相続時のリスク | 兄弟間トラブルになりやすい | 権利が明確でトラブル少ない |
| 税務上の取扱い | 贈与とみなされることも | 原則課税関係あり |
親の土地に家を建てる際は、「今だけでなく、将来どうなるか」を考えることが重要です。
行政書士は、使用貸借契約書や遺言書の作成など、法的トラブルを未然に防ぐためのサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。