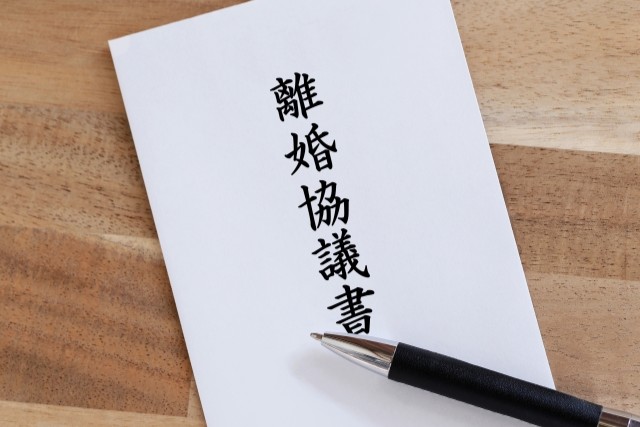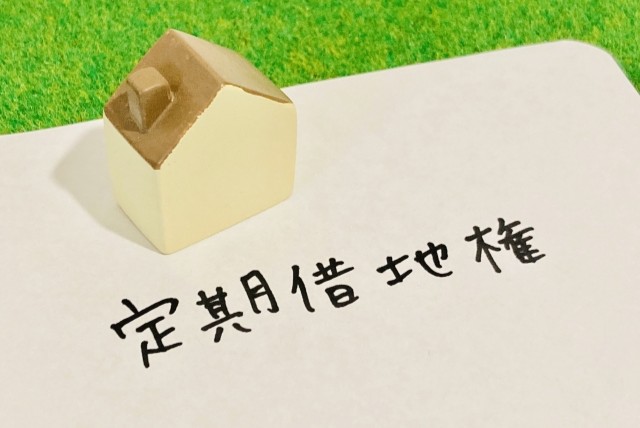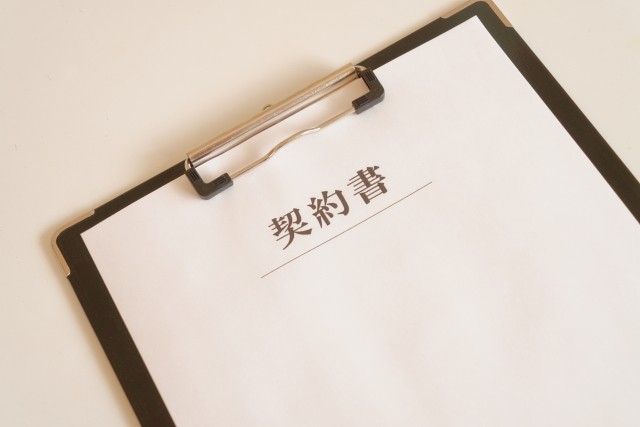契約書は、取引や約束ごとを文書として明確にし、後日のトラブルを防ぐために欠かせないものです。口約束でも契約は成立しますが、万一の紛争に備えるためには、文書による契約の証拠化が重要です。この記事では、契約書を作成する際に注意すべきポイントを、行政書士の視点から解説します。
契約書は「合意の証」
契約書は、当事者間での合意内容を確認・証明するための文書です。したがって、契約書の作成にあたっては「何について」「誰が」「どのような義務・権利を負うのか」を明確にする必要があります。文面が曖昧であると、解釈の違いが生じ、トラブルの原因となります。
たとえば、「納品はできるだけ早く行う」という表現ではなく、「〇年〇月〇日までに納品する」など、具体的な期日を明記しましょう。
契約の当事者を正確に記載する
契約の当事者が誰なのかを明確にすることは非常に重要です。法人との契約の場合は、法人名と代表者名を記載し、登記簿上の正式な名称を使います。個人の場合は、氏名・住所・生年月日などで特定できるようにします。
また、契約当事者に代理人がいる場合は、代理権の有無を確認し、必要に応じて委任状を添付することが求められます。
契約の目的や内容は明確に
契約の目的や対象となる商品・サービス、代金、納期、支払方法などは、できるだけ具体的に記載します。抽象的な記述はトラブルのもとになります。
【記載例】
- 商品の詳細:型番、数量、品質基準など
- 役務の範囲:業務内容、スケジュール
- 支払条件:支払日、振込先、分割払いの有無
契約期間と解除条件の明示
契約がいつからいつまで有効なのか、途中で解除できるのか、違約金や損害賠償の有無などを事前に決めておくことが大切です。契約期間を定めないと、トラブルが長期化する恐れがあります。
また、「契約違反があった場合には通知後〇日以内に是正されなければ契約を解除できる」など、解除条件を具体的に定めておくと、法的トラブルのリスクを軽減できます。
紛争解決方法の取り決め
契約違反や解釈の相違があった場合に、どのように解決するかを決めておくことも重要です。たとえば、以下のような文言を入れておくと安心です。
本契約に関して紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
特に取引相手が遠方の場合や、金額が大きい契約では、この取り決めが後々の負担軽減につながります。
印鑑・署名の正確性
契約書は当事者双方が署名または記名押印してはじめて効力を持ちます。法人の場合は代表者印(実印)、個人の場合は実印もしくは認印を使用するのが一般的です。
契約書によっては「記名押印」よりも「署名捺印」のほうが証拠能力が高くなることもあるため、重要な契約では署名を推奨します。
また、印紙税の対象となる契約書については、所定の収入印紙を貼付し、割印をすることを忘れないようにしましょう。印紙の貼付漏れは、後日税務署から過怠税を課される可能性があります。
契約書の原本管理と保管
契約書は通常、当事者双方が一通ずつ原本を保管します。「契約書は2通作成し、甲乙双方記名押印のうえ各自1通を保管する」と記載し、紛失や改ざんの防止に努めましょう。
紙の原本に加え、スキャンしたPDFデータなどを保管しておくと、万一の際にも迅速に対応できます。特に長期の契約や高額取引の場合は、電子保管も併用しましょう。
法的に無効となる条項に注意
契約書に記載された内容であっても、法律に反する条項は無効になります。たとえば、消費者契約において「いかなる場合も損害賠償請求はできない」といった条項は、消費者契約法により無効とされる可能性があります。
また、賃貸借契約や労働契約など、法律で定められた強行規定がある分野では、個別の合意が法令に優先されることはありません。法律の知識に基づいて、適法な契約内容とする必要があります。
テンプレートの流用リスク
インターネット上に公開されている契約書のテンプレートをそのまま使用すると、自社の実態や取引内容に合わない、不要な条項が残る、逆に必要な条項が抜けている、といったリスクがあります。
テンプレートはあくまでも参考にとどめ、実際の契約内容に合わせて修正・加筆することが重要です。不安がある場合は、専門家に確認してもらいましょう。
まとめ
契約書は「何かあったとき」のための備えであり、当事者の信頼関係を支える重要な書面です。些細な表現の違いが大きなトラブルにつながることもあるため、内容の明確化、法律との整合性、保管体制の整備など、細部まで気を配ることが求められます。
行政書士としては、契約内容のチェックや契約書の作成支援を通じて、トラブルを未然に防ぐお手伝いができます。契約書についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。