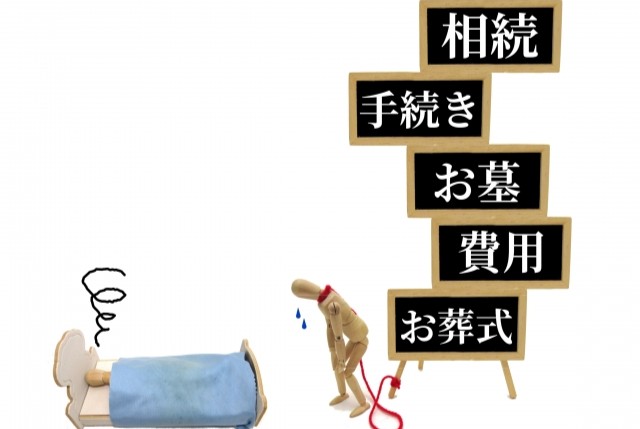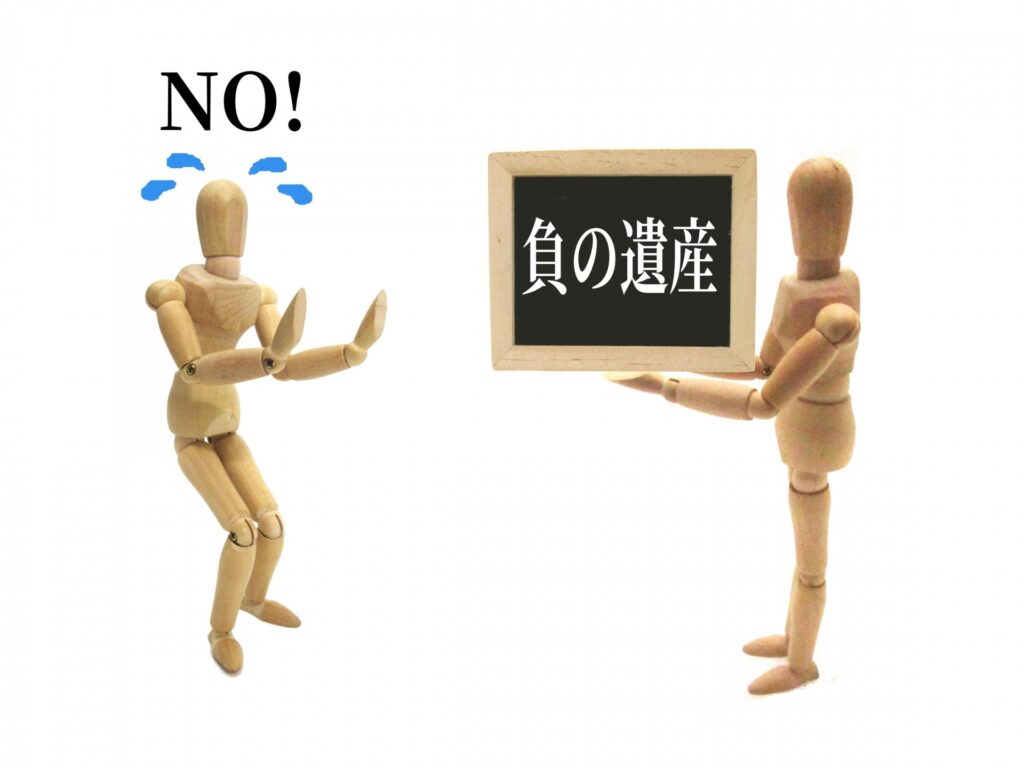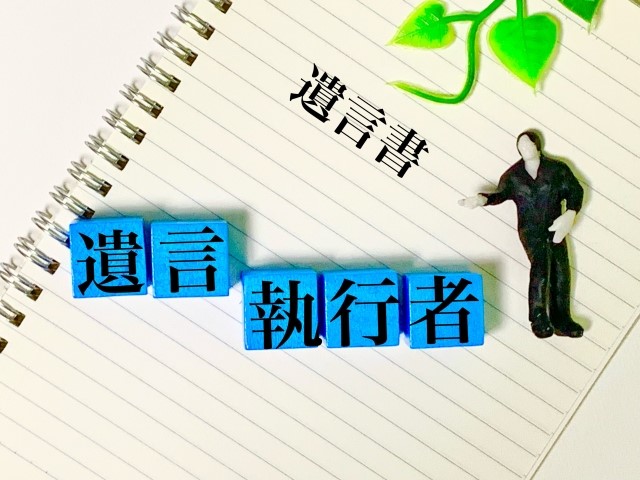遺言書は、亡くなった方が「誰に」「何を」残すのかを指定できる大切な手段です。しかし、そこに使うたった一言の違いで、思わぬトラブルを招くことがあります。
例えば、同じように見える「〇〇に財産を相続させる」と「〇〇に財産を遺贈する」という表現。実はこの二つは法律上の意味が大きく異なり、使い方を誤ると、登記や名義変更ができなくなったり、放棄ができなくなったり、遺された家族が困ってしまう可能性があるのです。
今回は、「相続させる」と「遺贈する」の違いを中心に、実際のトラブル事例や配偶者居住権に関する注意点まで含めて詳しく解説します。
「相続させる」と「遺贈する」の基本的な違い
■ 「相続させる」
- 対象は法定相続人に限る
- 遺言による遺産分割方法の指定(民法908条)にあたり、当然に効力が発生
- 単独で登記申請が可能(不動産など)
- 放棄する場合は家庭裁判所での相続放棄手続きが必要
- 放棄すると他の財産も一括して放棄扱い
■ 「遺贈する」
- 法定相続人でも第三者でもOK
- 贈与的性質をもつ単独行為(民法964条)
- 原則として受遺者の承認が必要
- 登記や引き渡しに相続人の協力が必要な場合がある
- 放棄(拒絶)は自由で、手続きも簡便(意思表示だけ)
実際に起きたトラブル事例:長男に「自宅を遺贈する」
あるご家庭で、父親が以下のような遺言を残していました。
「長男〇〇に、〇〇市〇〇町の自宅を遺贈する。」
父の真意は、「長男に家を引き継いでもらいたい」というシンプルなものでしたが、『遺贈する』と書かれていたことが思わぬ事態を招きました。
▼ 起きたトラブル:
- 遺贈された長男が自宅の登記をしようとしたが、他の相続人全員の協力が必要に。
- 次男が「そんな話は聞いていない」と反発して協力せず、登記不能に。
- 結果として、相続全体が長引き、兄弟間の関係が悪化。
→ もしこの文言が「相続させる」であれば、長男は単独で登記可能であり、他の相続人の協力は不要でした。
放棄できる?できない?その違いも重大
● 「相続させる」場合の放棄
「相続させる」と指定された財産を不要と考えても、放棄するには相続人としての放棄手続きが必要です。これは家庭裁判所への申述によって行い、一度放棄すると他のすべての相続財産も放棄扱いになります。
例:「自宅は要らないけれど預貯金は受け取りたい」 → NG(相続放棄は全部一括)
● 「遺贈する」場合の放棄(拒絶)
遺贈は承諾を要するため、受け取る人は受け取るかどうか自由に選べます。しかも、家庭裁判所への手続きも不要。単純に「辞退します」と意思表示すれば効力が発生しません。
例:「不動産は要らないけれど、他の財産は受け取りたい」 → OK
特に注意!「配偶者居住権」は必ず『遺贈する』で!
令和2年の法改正で導入された「配偶者居住権」は、配偶者が亡き夫・妻と住んでいた家に引き続き住み続けられるようにする新しい制度です。
ところが、この配偶者居住権について「相続させる」と書いてしまうと、配偶者はその権利だけを放棄することができず、相続そのものを放棄しなければなりません。
▼ 実務で問題になった例:
「配偶者居住権を妻〇〇に相続させる。」と記載された遺言。
この文言では、仮に妻が「住まいは子と同居するから不要」と思っても、居住権だけを放棄することはできません。放棄するならば、相続人として全財産を放棄する必要があるため、非常に不都合です。
▼ 正しい記載はこう!
「配偶者居住権を妻〇〇に遺贈する。」
このように書けば、配偶者は自由意思で受け取るかどうかを選択できるため、本人の生活状況や意向に応じた柔軟な対応が可能になります。
「相続させる」「遺贈する」の使い分け早見表
| 項目 | 相続させる | 遺贈する |
|---|---|---|
| 対象者 | 法定相続人のみ | 法定相続人・第三者いずれも可 |
| 効力発生 | 遺言によって当然に発生 | 受遺者の承諾により効力発生 |
| 登記などの実務 | 単独で手続き可能 | 他の相続人の協力が必要な場合あり |
| 放棄の可否 | 家庭裁判所での相続放棄が必要 | 自由に拒絶可能(手続き不要) |
| 配偶者居住権への適用例 | NG(本人の意思で辞退できない) | OK(柔軟な対応が可能) |
遺言書作成時の実務ポイント
- 対象者を意識して文言を使い分ける
→ 法定相続人には「相続させる」、第三者や柔軟性が必要な場合は「遺贈する」 - 放棄の可能性を想定する
→ 財産の性質や相手の生活状況によって、「拒絶できる余地」を残しておくことも重要 - 配偶者居住権には必ず「遺贈する」
→ 配偶者の意思を尊重し、トラブルを防ぐために - 専門家のチェックを受ける
→ わずかな表現の違いが法的トラブルの原因になります。行政書士や公証人の関与を強くおすすめします。
まとめ:たった一言が、大きな混乱を生む
「相続させる」と「遺贈する」の違いは、登記や放棄の可否だけでなく、家族の関係性や相続手続きの円滑さにも大きく影響します。配偶者居住権のように、法改正で新しく設けられた制度に対しては、より慎重な対応が求められます。
遺言書は、亡き人の想いをかたちにする大切な手段。その想いを正しく届けるために、言葉の選び方には細心の注意が必要です。
当事務所では、「伝わる遺言」「残された家族が困らない遺言」の作成をサポートしています。表現の違いがもたらす法的・実務的な影響まで丁寧にご説明し、ご相談者さまに最適な遺言書を提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。