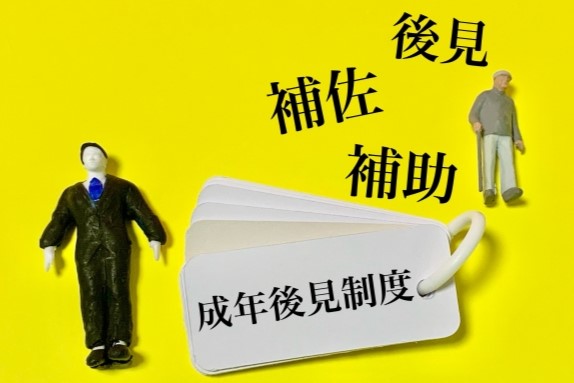近年、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。高齢化が進む日本において、認知症対策や相続対策、事業承継などの手段として注目されている制度です。しかし、家族信託にはメリットだけでなくデメリットもあります。本記事では、家族信託の基本的な仕組みとその利点・注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その家族が一定の目的に沿ってその財産を管理・運用・処分する仕組みです。法律的には「民事信託」と呼ばれ、信託法という法律に基づいて行われます。
たとえば、認知症に備えて「自宅不動産を長男に託し、管理や将来の売却などを任せる」といったケースが典型です。委託者(財産の持ち主)、受託者(託された人)、受益者(利益を受ける人)の三者によって構成されます。
家族信託の主なメリット
認知症になっても財産を凍結されない
もっとも大きなメリットは「認知症対策」です。通常、本人が認知症になると判断能力がなくなり、不動産の売却や預金の引き出しができなくなります。成年後見制度を利用する場合、手続きが煩雑で自由度も制限されます。
しかし家族信託を使えば、あらかじめ任せておいた家族(受託者)が財産の管理や処分を継続的に行うことができ、凍結のリスクを回避できます。
柔軟な財産承継ができる
家族信託は、「二次相続」以降の承継先も指定できるという特長があります。たとえば「自分が亡くなった後は妻へ、妻が亡くなった後は長男へ」といった指定が可能です。これは遺言書にはない、家族信託特有の柔軟性です。
共有不動産の管理がスムーズになる
複数人で所有している共有不動産は、管理や売却に全員の合意が必要です。信託によって受託者に一元的に管理させることで、スムーズに対応できます。
成年後見制度より自由度が高い
成年後見制度では、被後見人の利益保護が最優先されるため、不動産の売却や資産運用などは制限されることがあります。家族信託は事前に自由な契約内容を設計できるため、家族の状況に応じて柔軟に対応できるのが強みです。
家族信託の主なデメリット・注意点
仕組みが複雑で専門家の関与が不可欠
家族信託は法律的な構造が複雑で、契約書の作成には高い専門知識が必要です。内容を誤ると、相続トラブルの原因になったり、税務上不利になったりすることもあります。そのため、行政書士や司法書士、税理士などの専門家のサポートが不可欠です。
受託者には重い責任が課される
受託者は財産を託される立場であり、厳格な「善管注意義務」や「忠実義務」を負います。勝手な使い込みや、自己判断での不適切な運用は許されません。万一問題が生じた場合には、法的責任を問われる可能性もあります。
税務上の扱いが分かりにくい場合がある
家族信託には特有の税務処理が伴います。受益者の変更がある場合や、信託不動産の譲渡・売却が発生した場合などには、所得税・贈与税・相続税が関係してきます。誤った運用は課税トラブルの元になりますので、税理士との連携も必要です。
信託口口座の開設が難航することがある
信託財産として預金を管理する場合、金融機関で「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設する必要がありますが、すべての金融機関が対応しているわけではなく、開設手続きが煩雑な場合もあります。
家族信託を活用すべきケースとは?
次のような方には、家族信託の活用を検討する価値があります。
- 認知症による財産凍結を防ぎたい
- 相続人間のトラブルを防ぎたい
- 障がいを持つ子どもの将来を守りたい
- 事業承継をスムーズに行いたい
- 不動産の管理・処分を一任したい
ただし、全ての人にとって家族信託が最適というわけではありません。財産の規模や家族構成、希望する承継の形に応じて、遺言や成年後見、任意後見、法人化などと組み合わせて活用することが重要です。
まとめ
家族信託は、相続や老後の財産管理において強力な選択肢となります。特に、認知症対策や柔軟な相続設計を希望する方には大きなメリットがあります。一方で、制度が複雑であり、税務や法務の知識が必要不可欠なため、専門家のサポートを受けながら計画を立てることが大切です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じた家族信託の設計・契約書作成を丁寧にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。