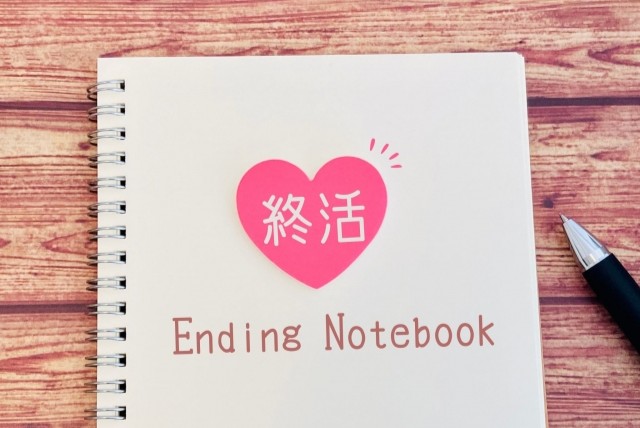自筆証書遺言は、遺言者が自ら書く遺言の形式であり、手軽に作成できる一方で、紛失や改ざんのリスク、家庭裁判所での検認が必要になるなどのデメリットがあります。これらの問題を解決するために、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。本制度を利用すると、法務局が遺言書を安全に保管し、遺言者の死後に相続人がスムーズに遺言内容を確認できるようになります。
制度のメリット
- 紛失や改ざんの防止
法務局が遺言書を厳重に保管するため、自宅での紛失や他者による改ざんのリスクがなくなります。 - 家庭裁判所の検認が不要
通常の自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要ですが、本制度を利用した遺言書は検認が不要となります。 - 遺言書の内容の明確化
保管の際に形式的な不備がないか法務局で確認されるため、無効となる可能性が低くなります。 - 相続人が円滑に遺言書を取得できる
相続人は遺言者の死後、法務局に請求することで遺言書を確認でき、手続きを円滑に進めることが可能になります。 - 指定者通知の仕組み
遺言者が希望すれば、遺言の内容を知る権利を持つ相続人や受遺者を「指定者」として登録できます。遺言者が亡くなった後、指定者には法務局から通知が届き、遺言書が保管されていることを知ることができます。これにより、遺言書の存在が確実に相続人に伝わり、相続手続きが円滑に進みます。 - 関係遺言書保管通知の仕組み
遺言者の死亡後、関係相続人等のうちいずれかの方が、法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた際に、その他の関係相続人等に対して、遺言書保管官が遺言書の保管を通知する制度です。この通知によって、すべての関係相続人等に遺言書が保管されていることが確実に伝わります。ただし、関係相続人等のいずれかが遺言書の閲覧等をしなければ、この通知は送付されません。
保管制度の利用方法
1. 遺言書の作成
- 遺言者が自筆で遺言書を作成します。
- パソコンやワープロでの作成は認められていません。
- 訂正の際には法律に従った適切な方法を取る必要があります。
2. 法務局へ申請
- 遺言者本人が住民票の写し、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参し、遺言書とともに法務局へ出向いて申請します。
- 保管申請には予約が必要です。
3. 保管料の支払い
- 保管手数料は3,900円です(2024年現在)。
4. 保管証の受領
- 保管が完了すると、遺言書の「保管証」が交付されます。
遺言書の閲覧・交付請求
生前の閲覧
遺言者本人のみ、法務局に申請することで自身の遺言書を閲覧できます。
相続開始後の閲覧・交付
遺言者の死亡後、相続人や受遺者は以下の手続きを経て遺言書を確認・取得できます。
- 法務局へ遺言書情報証明書の請求
- 相続人や受遺者は遺言者の死亡を証明する戸籍謄本などを提出し、遺言書の情報を取得します。
- 遺言書の写しの交付請求
- 必要に応じて遺言書の写しを請求できます。
- 遺言内容の確認と相続手続き
- 遺言内容を確認し、遺言に基づいた相続手続きを進めます。
- 指定者への通知
- 遺言者が生前に「指定者」を登録していた場合、遺言者の死亡後、法務局が指定者に対して遺言書保管の通知を行います。
- 関係遺言書保管通知の実施
- 関係相続人等のいずれかが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、法務局がその他の関係相続人等へ遺言書の保管通知を行います。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の課題を解決し、安全かつ確実に遺言を残せる制度です。法務局に保管を依頼することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、相続人にとっても手続きがスムーズになります。また、指定者通知や関係遺言書保管通知の仕組みを活用すれば、遺言書が確実に相続人に伝わり、相続トラブルの防止にも役立ちます。自筆証書遺言を検討している方は、ぜひこの制度の利用を検討してみてください。行政書士は、遺言書作成のサポートや、遺言に関する相談を受け付けています。適切な遺言を残すためにも、専門家に相談することをおすすめします。