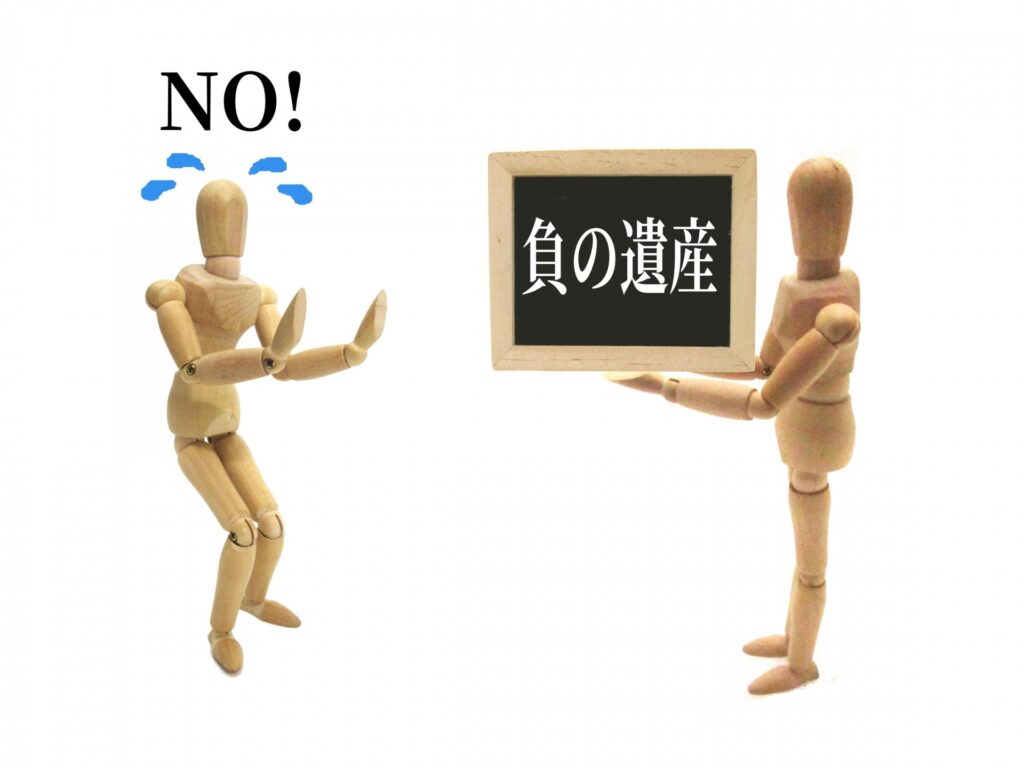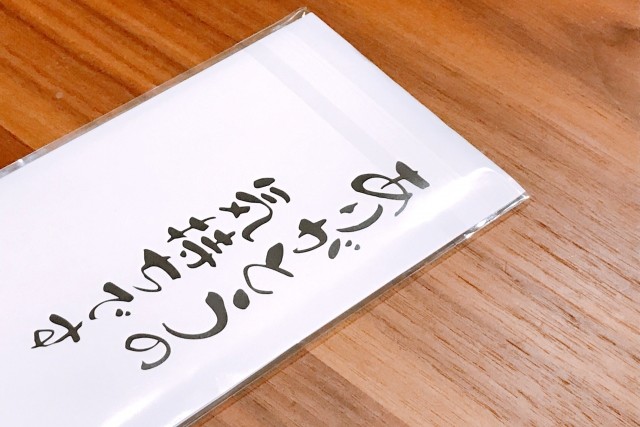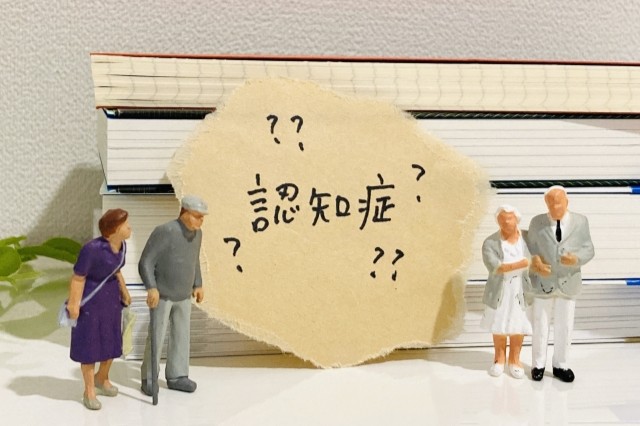
高齢の親が認知症になると、財産管理や相続の手続きが難しくなる可能性があります。特に、認知症が進行すると遺言書の作成や財産の処分ができなくなるため、事前の対策が重要です。本記事では、親の認知症を心配する方が取るべき相続対策について解説します。
成年後見制度の活用
認知症が進行し、親が自分で財産管理を行えなくなった場合、成年後見制度を利用することで、財産の管理や契約手続きをスムーズに行うことができます。
- 法定後見制度:認知症の進行後に家庭裁判所へ申し立てることで後見人が選任され、本人の財産管理を代行できます。
- 任意後見制度:認知症発症前に、本人が信頼できる人(子どもなど)と契約を結ぶことで、将来的に後見人として財産管理を委任できます。
遺言書の作成
認知症になる前に、親が自分の意思で遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続トラブルを防ぎ、スムーズな財産分割が可能になります。
- 公正証書遺言:公証役場で作成し、公証人が関与するため、認知症が疑われる場合でも有効性が高い。
- 自筆証書遺言:親が自分で書く遺言書。法務局で保管できる制度もあり、紛失や改ざんリスクを減らせる。
生前贈与の活用
認知症が進む前に、生前贈与を活用することで、相続税対策や財産分与の計画が可能になります。
- 年間110万円の基礎控除を活用:贈与税がかからない範囲で計画的に財産を移転。ただし、令和6年1月より相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるようになりました。
- 相続時精算課税制度の利用:親が60歳以上、子が18歳以上であれば、2500万円までの贈与が非課税。ただし、相続時に相続財産として課税対象となります。また、年間110万円の基礎控除も活用できるようになりました。
家族信託の導入
認知症対策として近年注目されているのが家族信託です。財産を信頼できる家族(受託者)に託し、親の生活を支える目的で管理・運用することができます。
- メリット:認知症発症後も柔軟に財産管理ができる。
- デメリット:契約内容の設計が複雑で、専門家のアドバイスが必要。
まとめ
親の認知症を心配する方にとって、早めの相続対策が重要です。成年後見制度、遺言書の作成、生前贈与、家族信託といった方法を適切に活用することで、親の意思を尊重しながらスムーズな相続を実現できます。相続対策についてお悩みの方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、認知症対策を含む相続相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。