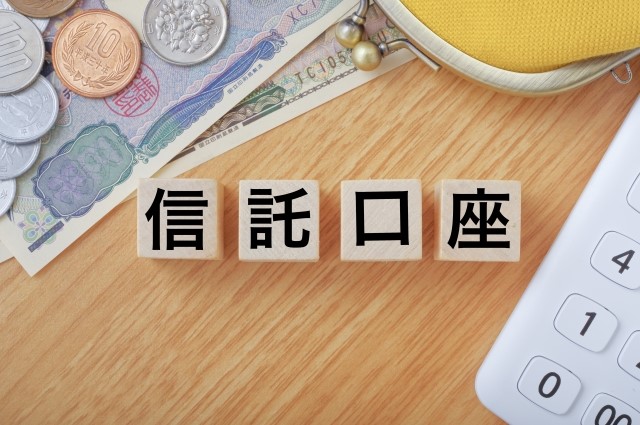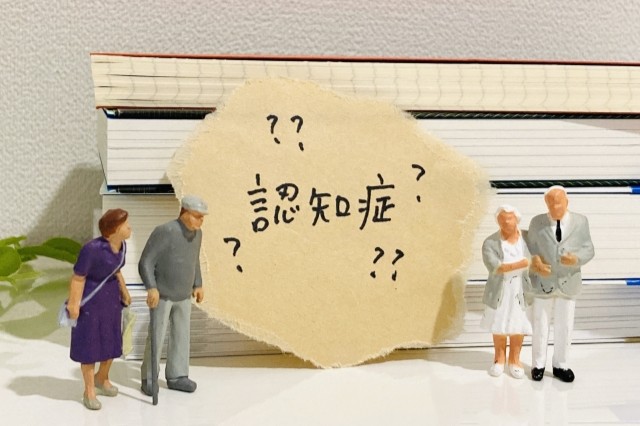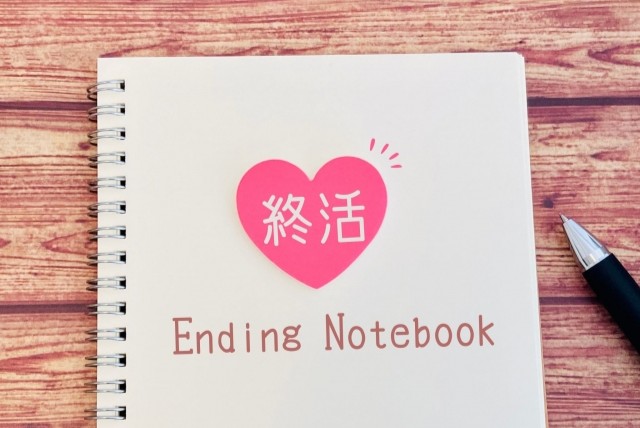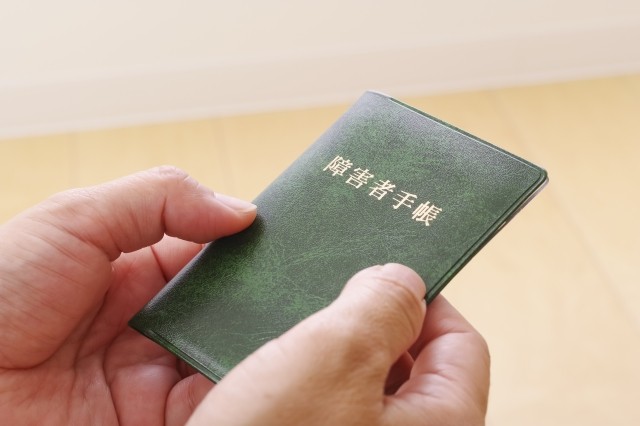
障がいのある子どもを持つ親にとって、将来の生活や財産管理の問題は大きな課題です。特に、親が高齢になったり亡くなったりした後、子どもが安心して生活を続けられるようにするための準備が重要です。
その解決策の一つとして注目されているのが「家族信託」です。本記事では、家族信託の基本的な仕組みや、障がい者の子どもを受益者にする場合のメリット・注意点について解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、家族間で財産管理や承継の仕組みを決めておく制度です。信託契約により、親(委託者)が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、受益者のために管理・運用してもらう仕組みです。
【基本的な登場人物】
- 委託者:財産を持っている人(例:親)
- 受託者:財産を管理・運用する人(例:兄弟や親族)
- 受益者:信託財産から利益を受ける人(例:障がいのある子ども)
家族信託は、成年後見制度とは異なり、財産管理の方法を事前に自由に決めておくことができます。
障がい者の子どもを受益者にする家族信託のメリット
障がいのある子どもを受益者にする場合、家族信託には以下のようなメリットがあります。
親亡き後も安定した財産管理が可能
親が元気なうちは問題ありませんが、万が一の際に財産管理をどのようにするかは重要な課題です。家族信託を設定しておけば、親が亡くなった後も、信頼できる受託者が子どもの生活費などを適切に管理できます。
成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる
障がいのある子どもが知的障がいや精神障がいを持っている場合、成年後見制度を利用することが一般的です。しかし、成年後見制度では財産の使い道が制限され、柔軟な運用が難しい場合があります。
一方、家族信託なら事前に「生活費として月◯万円を支給する」などのルールを決めておくことで、より実情に合った財産管理が可能です。
相続時の混乱を防ぐことができる
親が遺言を残さずに亡くなると、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、家族信託を活用すれば、事前に財産の管理方法を決めておけるため、相続時のトラブルを避けられます。
公的支援(障害年金・生活保護など)への影響を最小限にできる
障がい者の子どもが障害年金や生活保護を受けている場合、遺産を直接相続すると給付が減額・停止される可能性があります。家族信託を利用して「財産を一括で相続させるのではなく、毎月必要な分だけ支給する」仕組みにすることで、公的支援を維持しながら子どもの生活を支えることができます。
家族信託を設定する際の注意点
受託者を慎重に選ぶ
受託者には大きな責任が伴います。信頼できる家族がいれば良いですが、適任者がいない場合は専門家(信託会社など)に依頼する選択肢も検討しましょう。
契約内容を明確に決める
・生活費の支給方法(毎月・年単位など)
・財産の管理・運用ルール
・受託者が交代する場合の手続き
これらを契約書に明確に記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
税務面の影響を確認する
家族信託には贈与税・相続税が関係するため、税理士に相談して適切な設計を行うことが重要です。
まとめ
障がいのある子どもを受益者にする家族信託は、将来の財産管理を円滑にするための有効な手段です。特に、「親亡き後の生活が心配」「成年後見制度では柔軟な対応が難しい」と感じている方にとって、家族信託の活用は大きなメリットがあります。
ただし、信託契約の内容によっては思わぬ問題が発生することもあるため、専門家に相談しながら慎重に設計することをおすすめします。