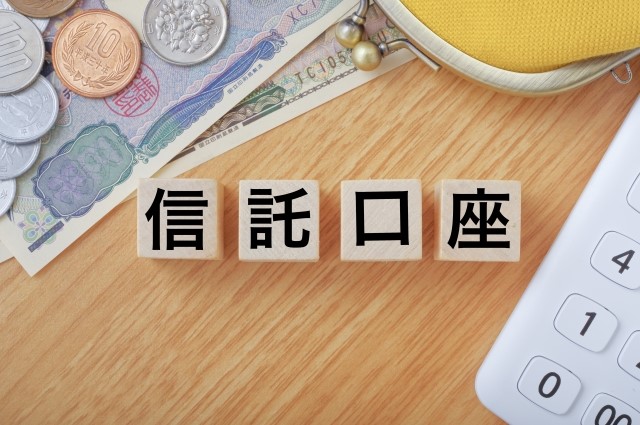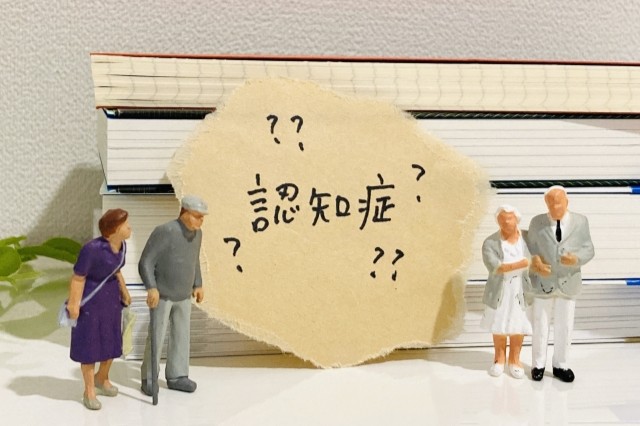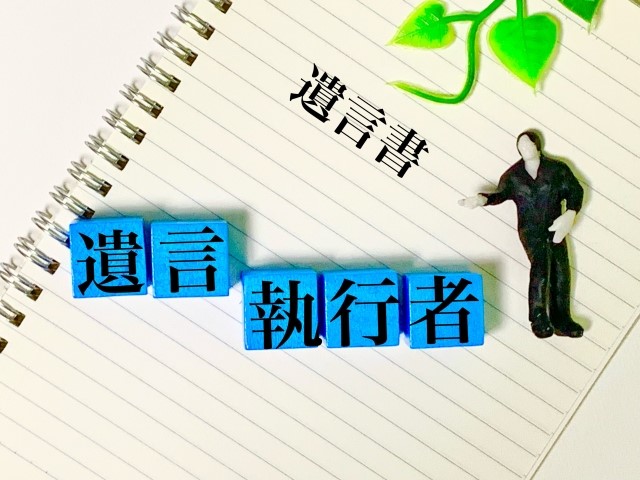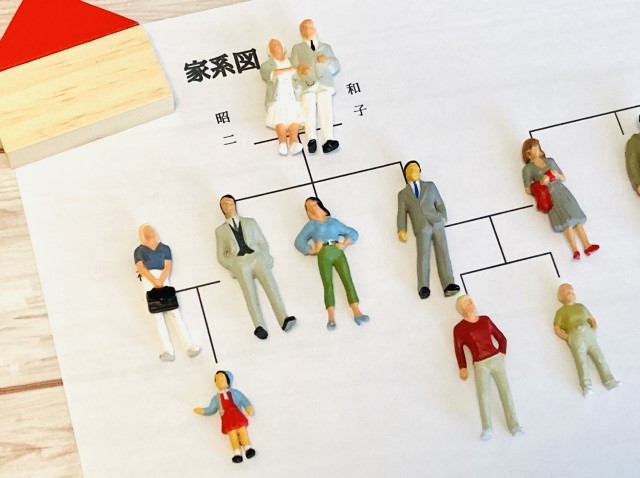
相続手続きを進める際、相続人を証明するために戸籍謄本を何度も提出する必要があります。しかし、「法定相続情報一覧図」を取得すれば、何度も戸籍謄本を提出する手間を省くことができます。本記事では、法定相続情報一覧図の取得方法について詳しく解説します。
1. 法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、法務局が発行する相続関係を証明する書類です。被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧図としてまとめ、戸籍謄本の代わりに相続手続きで使用できます。
メリット:
- 手続きの簡略化:戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなる。
- 無料で取得可能:手数料はかからない。
- 複数枚取得できる:相続手続きの際、必要な数だけ発行可能。
2. 取得の流れ
① 必要書類を準備する
法定相続情報一覧図を作成するために、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 申請者(相続人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 法定相続情報一覧図(案)(自分で作成する場合)
② 申請書を作成する
法務局で指定されている「法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書」を記入します。
③ 法務局へ申請する
書類が揃ったら、管轄の法務局へ申請します。申請方法は以下の3つです。
- 直接提出:法務局の窓口へ持参。
- 郵送申請:書類を郵送し、受領方法を指定。
- オンライン申請:一部の法務局では可能。
④ 法定相続情報一覧図を取得する
申請後、審査が行われ、問題がなければ「法定相続情報一覧図」が発行されます。通常1週間〜10日程度で交付されます。
3. 取得後の活用方法
法定相続情報一覧図は、以下のような相続手続きに活用できます。
- 金融機関での相続手続き(預金の解約や名義変更)
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 保険金の請求
- 株式や証券の相続手続き
4. まとめ
法定相続情報一覧図を取得することで、相続手続きの負担を大幅に軽減できます。特に、複数の手続きを同時に進める場合、戸籍謄本を何度も提出する手間が省けるため、ぜひ活用しましょう。
相続手続きでお困りの方は、行政書士に相談するのもおすすめです。正確な書類作成や手続きの代行を依頼することで、スムーズに相続を進めることができます。