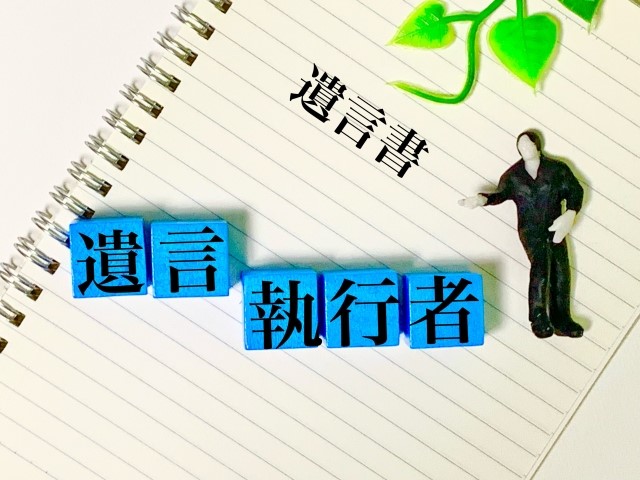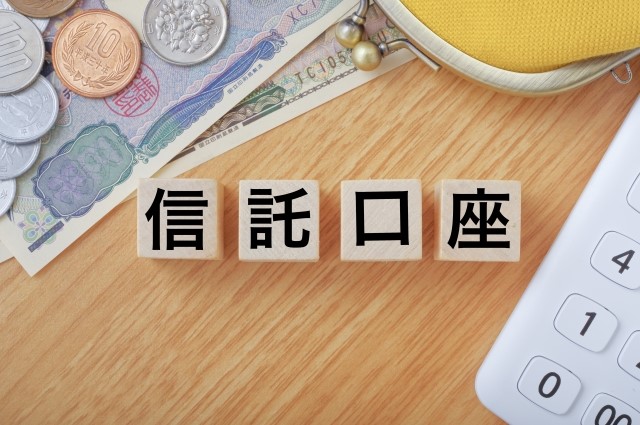近年、「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。特に不動産を所有している方にとって、相続や認知症対策の手段として注目を集めています。しかし、「自分にも関係があるのか?」「どんな人にとって有効なのか?」と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産の家族信託が有効なケースや対象となる人について、行政書士の立場からわかりやすく解説いたします。
そもそも家族信託とは?
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、自分の財産の管理や処分を信頼できる家族など(受託者)に任せ、受益者のためにその財産を運用・管理してもらう仕組みです。主に生前の財産管理や将来の認知症対策、相続対策として利用されます。
不動産信託の場合、たとえば「親が所有している土地や建物を、将来認知症になってもスムーズに活用できるよう、子に管理を任せておく」といった形で活用されます。
家族信託が有効な人の特徴
■認知症による資産凍結を避けたい人
もっとも多いのが、将来的な認知症リスクを見据えて、資産凍結を防ぎたいというニーズです。親が不動産を所有している場合、認知症になると売却や賃貸契約といった法律行為ができなくなります。成年後見制度を利用すれば手続きは可能ですが、自由な資産活用には制限があります。
家族信託であれば、元気なうちに子どもに管理権限を託すことができ、将来親が認知症になった後も不動産を柔軟に活用できます。
■相続対策を考えている人
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 「この不動産は長男に継がせたいが、他の子とのバランスも考慮したい」
- 「代々の土地を守っていきたい」
家族信託を使えば、不動産の「誰に・いつ・どのように」承継させるかをあらかじめ決めておくことが可能です。一般的な遺言では「一代先」までしか指定できませんが、家族信託なら「長男→その子ども→その孫」といった「次世代承継」も設計できます。
■共有名義の不動産を持つ人
兄弟や親子で不動産を共有している場合、ひとりでも意思能力を失えば、売却や賃貸などの活用ができなくなるリスクがあります。信託を活用して信託契約のなかで意思決定権限を集約することで、柔軟な運用が可能になります。
■遺言では対応しきれない事情がある人
例えば、
- 子どもに知的障害がある
- 再婚して前妻との子と現妻との子がいる
- 自分の死後、財産の行方が不安
こうした複雑な家庭事情の場合、家族信託を使えば、受益者を柔軟に設定できるため、きめ細かな財産管理と承継設計が可能です。
家族信託が「向かない」ケースもある?
有効なケースが多い一方で、家族信託が必ずしも適していないケースもあります。
- そもそも信託したい財産がない(不動産も金融資産も少額)
- 家族間の信頼関係が築けていない(受託者として任せられる人がいない)
- 高齢で判断能力がすでに衰えている(信託契約が結べない)
こうした場合は、他の方法(遺言、成年後見制度、任意後見など)を検討すべきです。
家族信託を検討するなら専門家に相談を
家族信託は非常に柔軟で有効な制度ですが、そのぶん設計が複雑で、契約内容によっては後のトラブルにつながる可能性もあります。特に不動産が絡む場合は、登記や税務上の手続きが伴います。
行政書士や司法書士、税理士などの専門家と連携して、家族の状況に合った信託設計を行うことが重要です。
まとめ:不動産の家族信託が有効な人とは
- 認知症対策として資産を凍結させたくない人
- 次世代へのスムーズな資産承継を考えている人
- 不動産の共有名義を整理・活用したい人
- 複雑な家庭事情で柔軟な財産管理をしたい人
こうした方にとって、家族信託は非常に有効な手段となり得ます。
「まだ元気だから」「うちは大丈夫」と思っていても、将来に備えた準備は早いに越したことはありません。不動産をお持ちの方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。