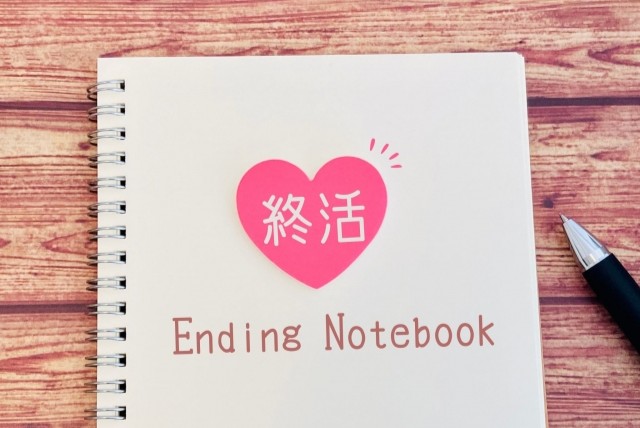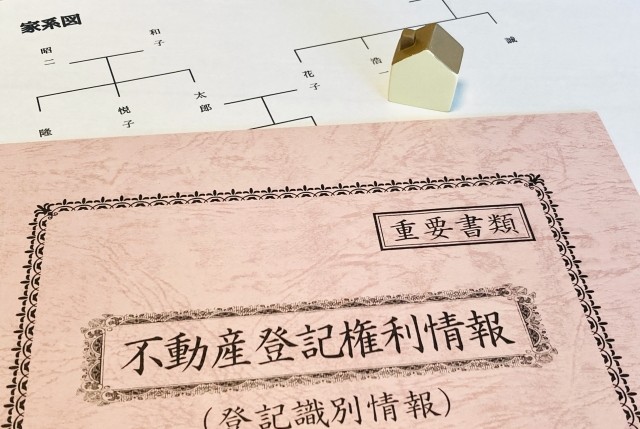相続において、「遺留分」と「特別受益」はしばしば争いの原因となる重要な概念です。この記事では、それぞれの意味と関係性について解説し、トラブルを避けるための対策を紹介します。
遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に譲渡したとしても、一定の相続人には最低限の相続分が保証されます。
遺留分を主張できる相続人
遺留分を主張できるのは、
- 配偶者
- 直系卑属(子や孫)
- 直系尊属(父母)※ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分は法定相続分の一定割合で決まります。
- 配偶者や子がいる場合:遺産の 1/2
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺産の 1/3
例えば、遺産が1億円で相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分は1億円の1/2で5,000万円。そのうち配偶者と子で法定相続分に応じて分けることになります。
特別受益とは?
特別受益(とくべつじゅえき)とは、生前に被相続人から特定の相続人が受けた特別な贈与や遺贈のことを指します。特定の相続人だけが多額の贈与を受けていると、他の相続人との間で不公平が生じるため、相続財産に加算(持ち戻し)して計算されることがあります。
特別受益の対象となる例
- 生前贈与された不動産
- 高額な学費(医大や海外留学の費用など)
- 結婚資金や開業資金の援助
- 事業承継のための資産移転
特別受益の計算方法は「持ち戻し計算」と呼ばれ、相続開始時点の遺産に特別受益を加えた上で、相続分を算定します。
ただし、令和元年の民法改正により、持ち戻しの対象となる生前贈与は相続開始前10年以内のものに制限されることになりました。
遺留分と特別受益の関係
特別受益がある場合、遺留分の計算にも影響を及ぼします。たとえば、被相続人の生前に特定の相続人が多額の贈与を受けていると、遺産全体の価額を算定する際に持ち戻されるため、遺留分を侵害している可能性があります。
具体例
- 被相続人の遺産:5,000万円
- 生前贈与された特別受益:2,000万円(子Aが受領)
- 相続人:配偶者と子A、子Bの3名
- 遺留分の計算基礎額=5,000万円+2,000万円=7,000万円
- 遺留分の合計(1/2)=3,500万円
- それぞれの遺留分権利額:配偶者1,750万円、子A 875万円、子B 875万円
この場合、子Aはすでに2,000万円を受け取っているため、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
トラブルを防ぐための対策
- 遺言書を活用する
- 遺言書に遺留分を考慮した内容を記載し、不公平感を減らす。
- 遺留分を侵害する可能性がある場合は、理由を明記する。
- 生前贈与の計画的な実施
- 特別受益になりうる贈与を慎重に行い、他の相続人とのバランスを考える。
- 「持ち戻し免除の意思表示」を明確にすることで、遺産分割の際に影響を軽減できる。
- 遺留分侵害額請求の理解
- 遺留分を侵害された相続人は、侵害された分を請求することができる。
- ただし、請求できる期間(除斥期間)は相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内なので、早めの対応が必要。
まとめ
遺留分と特別受益は、相続における公平性を保つための重要な制度ですが、時に争いの火種にもなります。適切な生前対策や遺言書の作成によって、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
相続に関するお悩みがあれば、専門家である弁護士や司法書士、行政書士に相談することで、円滑な相続手続きを進めることができます。