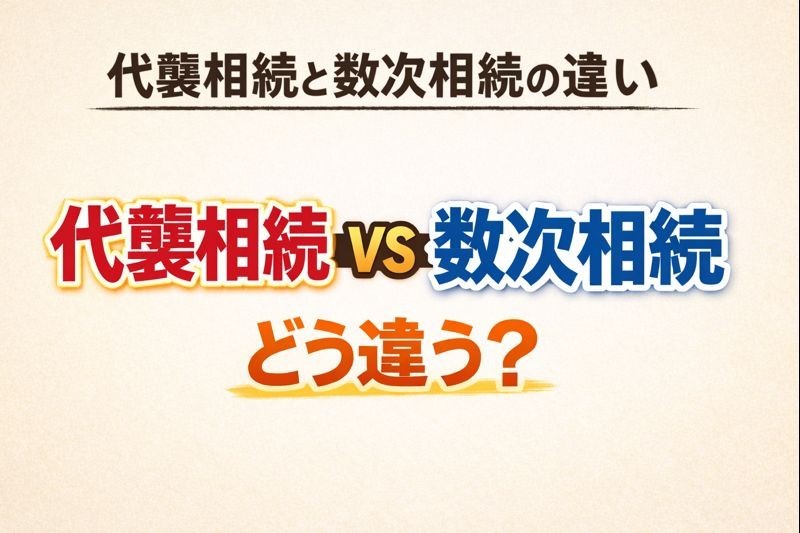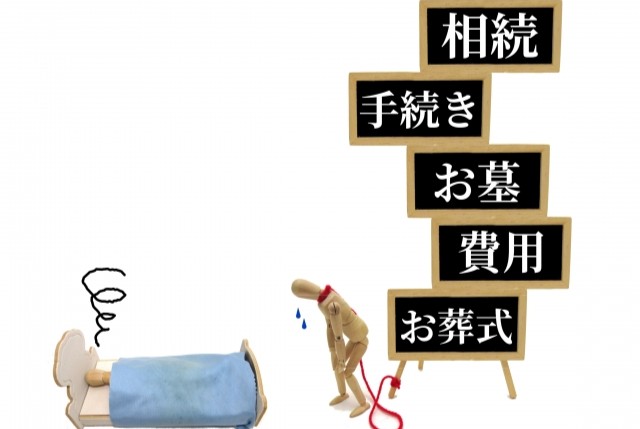
近年、少子高齢化や単身世帯の増加に伴い、「死後の手続きは誰がしてくれるのか?」という不安を抱える方が増えています。相続人がいない場合や、親族と疎遠な場合、自分が亡くなった後の事務手続きを誰かに任せる必要があります。そこで注目されているのが 「死後事務委任契約」 です。本記事では、死後事務委任契約の仕組みと、遺言との相乗効果について詳しく解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する各種手続きを、信頼できる第三者(行政書士、司法書士、弁護士、親族など)に委任する契約 です。
相続に関する手続きは相続人が行いますが、それとは別に、役所への届出、葬儀の手配、遺品整理、契約の解約など、相続財産とは直接関係のない事務手続きが数多く発生します。これらをスムーズに進めるために、死後事務委任契約が活用されます。
死後事務委任契約で依頼できる内容
死後事務委任契約では、以下のような手続きを依頼できます。
| 業務内容 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 葬儀・納骨関連 | 葬儀の手配、火葬・納骨、散骨の実施 |
| 役所関係の手続き | 死亡届の提出、健康保険・年金の手続き |
| 契約の解約 | 賃貸借契約の解除、公共料金・クレジットカードの解約 |
| 遺品整理・住居の整理 | 家財処分、清掃、家屋の明け渡し |
| インターネット関係 | SNSアカウント削除、サブスク解約 |
| ペットの引き渡し | 飼育先の手配、引き渡し |
死後事務委任契約のメリット
✅ 親族に負担をかけない
→ 遠方に住む親族や、相続人がいない場合でも、スムーズに手続きを進められる。
✅ 自分の希望を実現できる
→ 葬儀の形式や納骨方法を事前に決めておける。
✅ トラブルを防ぐ
→ 親族間の意見の食い違いを避けられる。
遺言と死後事務委任契約の違い
死後事務委任契約と遺言はどちらも「亡くなった後の手続き」に関するものですが、目的が異なります。
| 比較項目 | 死後事務委任契約 | 遺言 |
|---|---|---|
| 目的 | 事務手続きを委任 | 財産の分配を指示 |
| 内容 | 葬儀、契約解約、遺品整理など | 遺産の分割方法、相続人の指定 |
| 執行人 | 受任者(行政書士・弁護士など) | 遺言執行者(相続人・専門家) |
| 法律上の効力 | 契約に基づく | 民法に基づく(法的強制力あり) |
つまり、「相続財産の分配」については遺言で、「死後の事務手続き」については死後事務委任契約で対応する のが理想的です。
遺言と死後事務委任契約の相乗効果
遺言と死後事務委任契約を組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続き が可能になります。
相乗効果の例
🔹 遺言で相続人を指定し、死後事務委任契約で手続きを依頼
→ 遺言で財産を特定の人に相続させつつ、死後事務委任契約で賃貸借契約の解約や公共料金の精算を専門家に依頼する。
🔹 葬儀や納骨方法を指定する
→ 遺言では「〇〇寺に納骨してほしい」と書き、死後事務委任契約で実際の手続きを行政書士に依頼。
🔹 財産管理と死後の整理を一括で手配
→ 生前は財産管理委任契約や任意後見契約を結び、死後は死後事務委任契約で事務手続きを行い、最終的に遺言で相続を確定させる。
このように、遺言と死後事務委任契約を併用することで、相続人や関係者の負担を大幅に軽減 できます。
死後事務委任契約の締結方法
契約を締結するには、以下の手順を踏みます。
- 依頼する内容を決める
- 受任者を決定する(行政書士・司法書士・弁護士など)
- 契約書を作成する(公正証書が望ましい)
- 委任に必要な費用を準備する(預託金の用意)
- 遺言との整合性を確認する
特に、公正証書で契約を作成すると、トラブルを防ぎやすくなります。
まとめ|安心の終活を実現するために
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを円滑に進めるための重要な制度です。
しかし、財産の相続は死後事務委任契約では処理できません。そこで、遺言と組み合わせることで、財産と事務手続きの両方をしっかり管理できるようになります。
「自分の死後、親族に迷惑をかけたくない」「相続と事務手続きをスムーズに進めたい」という方は、ぜひ遺言と死後事務委任契約をセットで検討してみてください。
行政書士や専門家に相談することで、最適なプランを組むことができます。
終活の第一歩として、まずは一度ご相談ください。