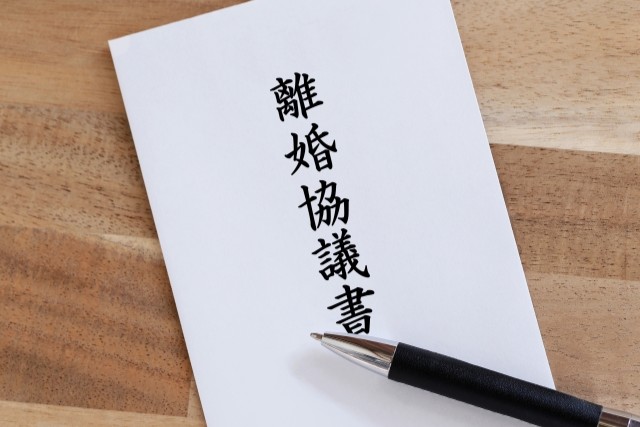2025年10月1日より、公正証書の作成手続きが大きく変わります。これまでの公証役場での対面中心の手続きから、デジタル化された新しい仕組みが導入されることになりました。今回は、その概要や利用方法、メリット・注意点について解説します。
※ 10月1日以降、まずは順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
公正証書とは?
公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な文書のことです。
代表的なものに以下があります。
- 遺言公正証書:相続に備えるための遺言書
- 任意後見契約公正証書:将来の判断能力低下に備える契約
- 金銭消費貸借契約公正証書:借金返済に関する強制執行認諾条項付き契約
公正証書は裁判になった際の証拠力が非常に強く、強制執行まで可能なケースもあるため、トラブル防止のために広く利用されています。
デジタル化の背景
これまで、公正証書を作成する際には、当事者が公証役場に出向き、紙媒体でやり取りを行う必要がありました。
しかし、
- 高齢者や地方在住者にとって公証役場が遠い
- 書類準備に時間と手間がかかる
- ペーパーレス化・行政手続DXの流れ
といった課題から、デジタル化が検討され、ついに2025年10月から導入されることとなりました。
新しいデジタル化手続きの流れ
日本公証人連合会の案内によると、デジタル化後の手続きは次のように進みます。
- 事前準備(オンライン申請)
当事者は、自宅や事務所から専用の「公証手続き電子システム」にアクセスし、必要事項を入力。本人確認資料のデータ送付も可能です。 - 本人確認(オンライン対応可)
公証人は、オンライン会議システムを用いて本人確認を行うことができます。従来通り対面確認も選択可能です。 - 契約内容の確認・修正
公証人と当事者がオンラインで内容を確認し、必要に応じて修正。 - 電子署名・完成
当事者が電子署名を行い、公証人も電子署名を付与。これにより、法的効力を持つ「電子公正証書」が完成します。 - 保存・交付
作成された電子公正証書は、公証役場のシステムに保存され、当事者には電子データとして交付。希望すれば紙での謄本交付も可能です。
デジタル化によるメリット
- 公証役場に行く回数が減る
遠方に住んでいる方や高齢者でも、オンラインで手続きを進められるようになります。 - 迅速化・効率化
書類のやり取りや修正がスムーズになり、作成までの時間が短縮されます。 - ペーパーレス化
電子署名によって紙のやり取りが減少し、保管も電子化されます。 - セキュリティの強化
データは公証人連合会のシステムで厳重に管理されるため、改ざんや紛失のリスクが低減されます。
注意点と従来との違い
- 電子証明書やマイナンバーカードの利用が前提
本人確認のため、一定のデジタル環境が必要です。 - 高齢者やITに不慣れな人にはサポートが必要
完全オンラインでは不安な方には、従来通り公証役場での手続きも可能です。 - 電子データの保存方法に注意
電子公正証書は改ざん不可ですが、閲覧や交付の方法をきちんと確認しておく必要があります。
まとめ
2025年10月1日から始まる「公正証書作成手続きのデジタル化」は、公証制度における大きな改革です。
これにより、
- 遠方や高齢の方も利用しやすくなる
- 手続きがスピーディーに進む
- 安全性・利便性が向上する
といったメリットが期待されます。
一方で、電子署名やシステム利用に不慣れな場合は、公証役場や専門家のサポートを得ながら進めるのが安心です。
相続・契約・後見など、人生の大切な局面で利用される公正証書。デジタル化によって、より身近で利用しやすい制度へと進化していきます。
👉 ご自身やご家族の遺言、公正証書作成を検討されている方は、早めに専門家へ相談してみましょう。