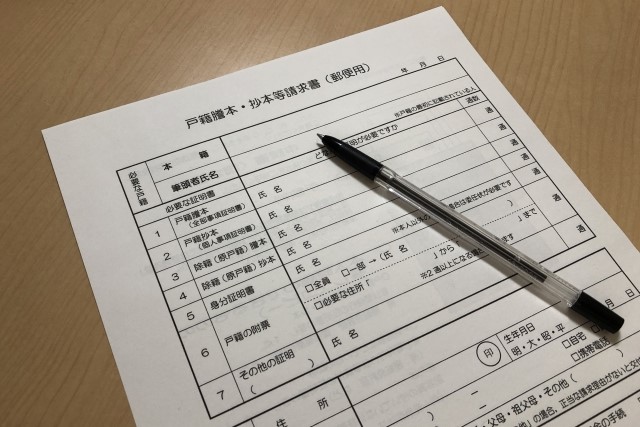相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれている場合、通常の相続手続きとは異なる配慮が必要になります。未成年者は法律上、単独で遺産分割協議を行うことができず、代理人の関与が必要です。本記事では、未成年者が相続人となるケースの注意点と具体的な手続きについて解説します。
1. 未成年者が相続人になるケースとは?
未成年者が相続人となる代表的なケースとして、次のような状況が考えられます。
- 親が亡くなり、子どもが相続人になる場合
たとえば、父親が亡くなった場合、母親と子ども(未成年)が相続人になることがあります。 - 祖父母の財産を孫が相続する場合
親がすでに他界しており、代襲相続(親に代わって子が相続する制度)が発生すると、未成年の孫が相続人となることがあります。
未成年者が相続人となる場合、特に注意しなければならないのが 遺産分割協議 です。
2. 未成年者は単独で遺産分割協議ができない
民法では、未成年者は法律行為を単独で行うことができません(民法5条)。そのため、未成年者が遺産分割協議に参加する場合には 法定代理人(通常は親権者)が代理することになります。
しかし、相続人が未成年者とその親(親権者)だけの場合、問題が発生します。
親が代理できないケース
未成年の子と親がともに相続人である場合、親が子の代理人となると 利益相反(お互いの利益が対立する状態)となり、代理が認められません。
<例>
- 父親が亡くなり、相続人が母と未成年の子どもだけの場合
- 遺産分割協議で「母が全て相続する」と決めると、子どもの取り分がなくなる可能性がある
このような状況では、親が子の代理を務めることができません。
3. 「特別代理人」の選任が必要
親が未成年者の代理人になれない場合、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任する必要があります(民法860条)。
特別代理人の選任手続き
- 家庭裁判所に申し立て
- 申立人:親権者または利害関係人
- 申立先:未成年者の住所地の家庭裁判所
- 必要書類:
- 申立書
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議案
- その他必要書類(裁判所の指示による)
- 特別代理人の選任
- 家庭裁判所が適切な代理人を選任
- 弁護士や親族などが選ばれることが多い
- 特別代理人が遺産分割協議に参加
- 特別代理人が未成年者の利益を考慮して協議を進める
特別代理人を選任することで、未成年者の権利が適正に守られます。
4. 遺産分割協議での注意点
未成年者が相続人となる場合、特別代理人を選任したうえで、以下の点に注意して遺産分割協議を進めましょう。
未成年者の相続分を確保する
民法では、相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されています。未成年者だからといって、不当に少ない分配になることは避けるべきです。
不動産の相続に注意
未成年者が不動産を相続すると、管理や売却が難しくなることがあります。管理が困難な場合は、代わりに現金で分配する方法も検討しましょう。
早めに特別代理人の手続きをする
遺産分割協議を円滑に進めるためには、特別代理人の選任手続きを早めに進めることが重要です。相続手続きが長引くと、相続税の申告期限(10か月以内)に間に合わなくなるリスクもあります。
5. まとめ
未成年者が相続人になる場合、法律上の制約があるため注意が必要です。特に、親が代理人になれないケースでは、特別代理人を選任する手続きが必要となります。
重要ポイント
✅ 未成年者は単独で遺産分割協議ができない
✅ 親が代理人になれない場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する
✅ 遺産分割協議では未成年者の相続分を適正に確保する
相続手続きには専門知識が必要なため、行政書士などの専門家に相談することでスムーズに進められます。特に、未成年者が相続人となるケースでは、法律の規定を理解し、適切な手続きを進めることが大切です。