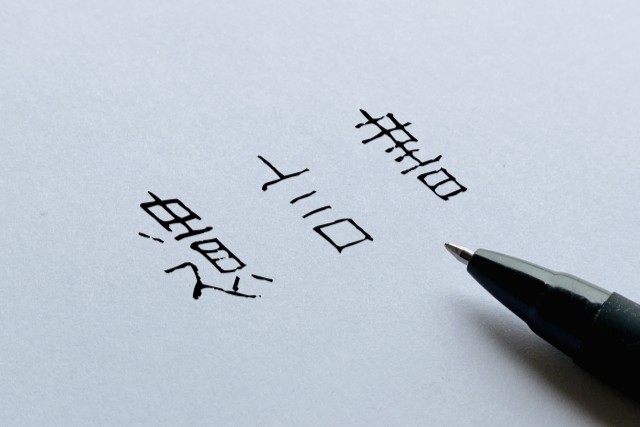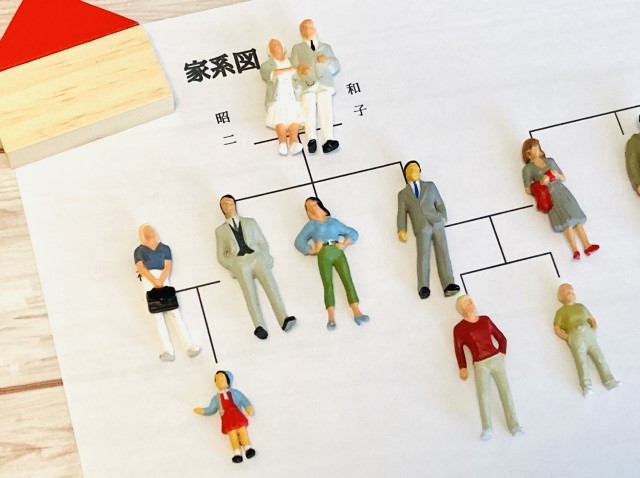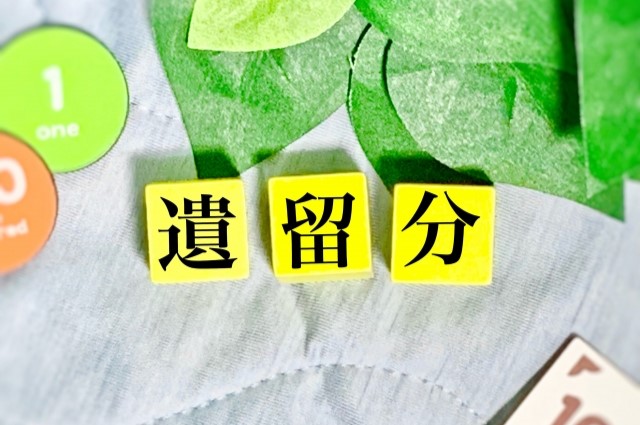
相続において「遺留分」という言葉を耳にすることがあります。遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる遺産の割合を指します。被相続人が遺言によって遺産を自由に処分したとしても、この遺留分を侵害することは認められません。
例えば、被相続人が全財産を特定の相続人や第三者に譲るという遺言を残した場合でも、遺留分を有する法定相続人はその権利を主張し、侵害された遺留分を取り戻すことが可能です。
遺留分の対象となる相続人
遺留分を持つ権利は、すべての法定相続人に与えられるわけではありません。以下の相続人に限定されています:
- 配偶者
- 直系卑属(子ども、孫など)
- 直系尊属(親、祖父母など)
兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分の権利を有しません。これにより、被相続人が兄弟姉妹に遺産を譲らない遺言を残したとしても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。具体的には次の通りです:
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺産全体の1/3
- 直系卑属や配偶者が相続人の場合:遺産全体の1/2
例えば、遺産が1,000万円で直系尊属(親)のみが相続人である場合、遺留分はその1/3である333万3,333円です。両親がいる場合は、父は1/6の166万6,667円、母は1/6の166万6,667円となります。
一方、配偶者と子どもが相続人の場合、遺留分は1/2の500万円に相当し、配偶者と子が1人の場合、配偶者は1/4の250万円、子は1/4(1/4÷1人)の250万円となります。そして、配偶者と子が2人の場合は、配偶者は1/4の250万円、子はそれぞれ1/8(1/4÷2人)の125万円となります。さらに、配偶者と子が3人の場合は、配偶者は1/4の250万円、子はそれぞれ1/12(1/4÷3人)の83万3,333円となります。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という法的手続きを行うことができます。この手続きの主な流れは以下の通りです:
- 内容証明郵便で請求 遺留分を侵害している相続人や第三者に対し、内容証明郵便で遺留分侵害額を請求します。
- 交渉と合意 当事者間で話し合い、遺留分の支払いについて合意します。
- 調停または訴訟 合意が得られない場合、家庭裁判所で調停や訴訟を行います。
請求には期限があり、遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、遺留分請求権は失効します。
遺留分を巡るトラブルと対策
遺留分に関連するトラブルは少なくありません。被相続人が遺言で特定の相続人に多くの財産を譲ろうとした場合、他の相続人が遺留分を主張して争いになるケースがよく見られます。
このようなトラブルを防ぐためには、次の対策が有効です:
- 遺言書の作成 遺留分を考慮した上で遺言書を作成し、相続人間の争いを未然に防ぐことが重要です。
- 生前贈与の活用 生前に相続人へ財産を分配することで、遺産分割の際のトラブルを減らすことができます。ただし、生前贈与も遺留分算定の対象となる場合があるため注意が必要です。
- 専門家への相談 相続に詳しい行政書士や弁護士に相談し、遺留分や遺産分割の計画を立てることがトラブル回避の鍵となります。
まとめ
遺留分は、法定相続人が最低限確保できる権利として重要な役割を果たしています。一方で、遺留分を巡る争いは家族関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、遺留分を考慮した遺言書の作成や適切な手続きが求められます。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、相続手続き全般に関するサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。