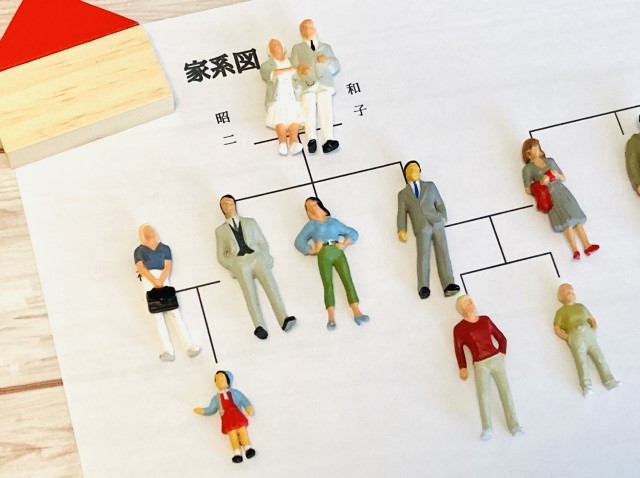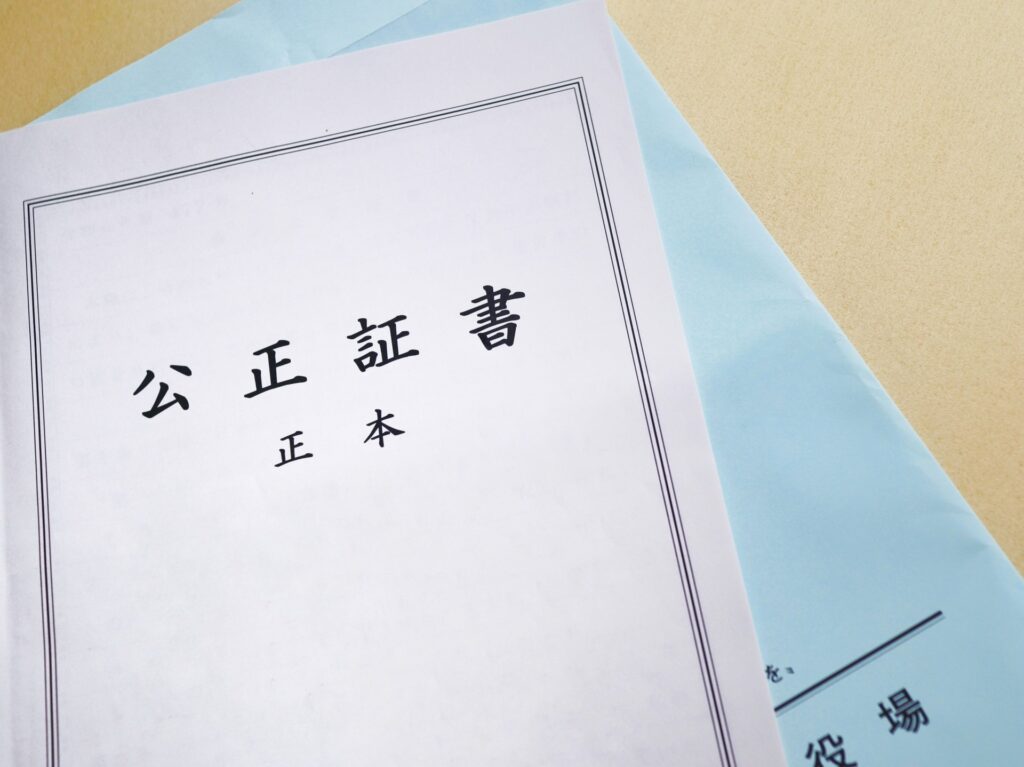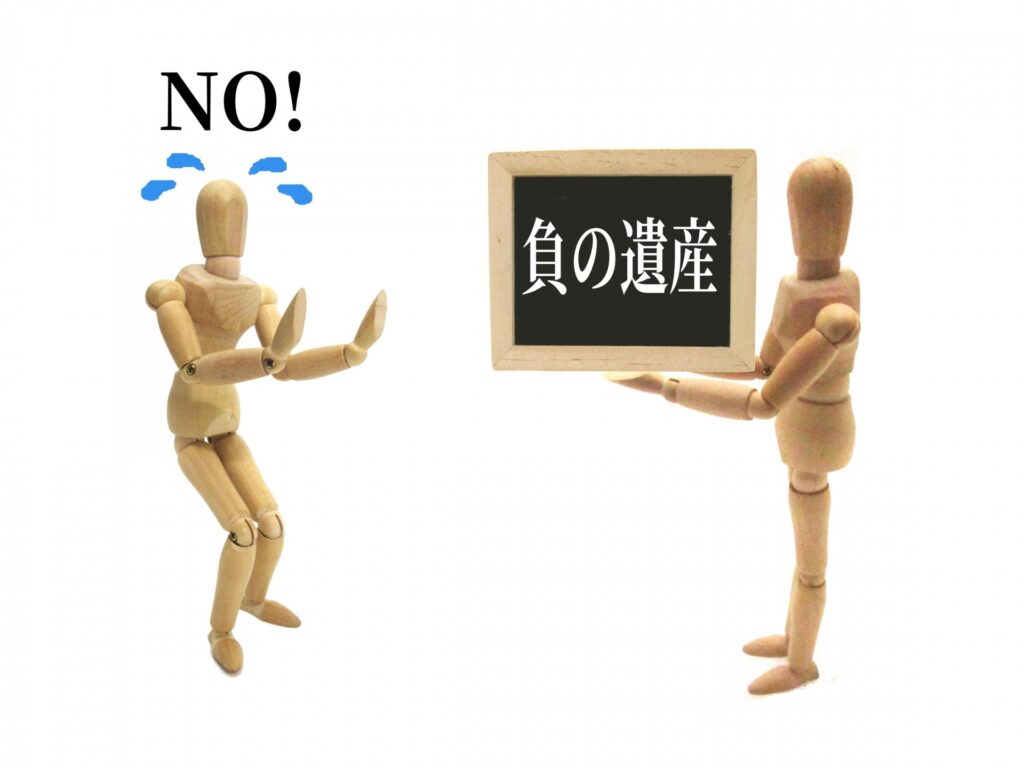相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の不動産が兄弟姉妹などの相続人に承継されます。その際、遺言書や遺産分割協議で特定の相続人に単独相続させる取り決めをしていない場合、不動産は自動的に「共有」という形で相続人に引き継がれます。
例えば、父が所有していた土地を長男と次男が相続した場合、登記上は「長男1/2、次男1/2」と共有名義になります。
一見平等に分けたように思えても、共有には多くのトラブルの種があります。今回は、兄弟間で共有になった土地のデメリットと、解消するための具体的方法について解説します。
共有土地の問題点
売却や活用がしにくい
共有不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。兄弟の一人が反対すれば売却はできません。また、建物を建てたり貸したりする場合も原則として共有者全員の同意が必要です。
維持管理や固定資産税の負担
固定資産税や修繕費は持分に応じて負担しなければなりません。しかし、一方の兄弟が支払いを拒否すると、残りの相続人にしわ寄せがきます。
将来の相続で権利関係が複雑化
兄弟間で共有のまま放置すると、次の世代に相続が発生した際、さらに共有者が増えてしまいます。従兄弟や姪甥など、縁が薄い親族と共同所有することになり、合意形成はますます困難になります。
共有状態を解消する方法
共有のままでは不動産の利活用が難しいため、できるだけ早めに解消することが望ましいです。代表的な方法を紹介します。
遺産分割協議での単独相続
相続開始直後であれば、遺産分割協議を行い、特定の相続人が土地を単独相続する形にするのが一番スムーズです。その代わりに、他の兄弟には預貯金や他の財産を多めに配分する、あるいは代償金(現金)を支払う方法があります。
持分の売買(代償による解消)
既に共有登記されてしまった場合でも、一方の相続人が他方の持分を買い取ることで単独所有にできます。
例えば、長男が次男の1/2持分を買い取れば、長男の単独所有となり、自由に処分できます。
第三者への売却
兄弟間で合意ができない場合、土地全体を売却し、その代金を持分割合で分ける方法があります。
ただし不動産市場では「共有持分」だけを売るのは価値が低く、買い手も限定的です。やむを得ない場合を除き、土地全体をまとめて売却する方が有利です。
共有物分割請求訴訟
話し合いで解決できない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることができます。民法では共有はいつでも解消できると定められているため、訴訟を起こせば必ず分割方法が決まります。
裁判所が取る方法は主に以下の3つです。
- 現物分割:土地を分筆して物理的に分ける方法。
- 代償分割:特定の相続人が土地を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法。
- 換価分割:土地を売却し、その代金を分ける方法。
ただし訴訟になると時間も費用もかかり、人間関係が悪化するリスクが高いため、できるだけ協議で解決するのが望ましいです。
共有解消の手順と注意点
- 現状の確認
登記簿を確認し、持分割合を把握します。 - 兄弟間での話し合い
土地を残したいのか、売却したいのか、各人の意向を確認します。 - 評価額の算定
不動産業者や専門家に依頼して時価を確認します。適正な評価がなければ代償金額などで不公平感が生じます。 - 方法の選択
協議でまとまれば「持分売買」「代償分割」「売却」などを実行します。 - 契約・登記の手続き
共有持分の移転や売却には必ず登記が必要です。司法書士に依頼すると安心です。
まとめ
兄弟間で相続した土地を共有のままにしておくと、活用が難しいだけでなく、将来の相続で権利関係が複雑化する大きなリスクがあります。
解消方法としては、
- 遺産分割協議で単独相続にする
- 持分を買い取って単独所有にする
- 売却して代金を分ける
- 裁判で共有物分割を求める
といった選択肢があります。
相続の場面では感情的な対立が生じやすいため、専門家を交えて冷静に手続きを進めることが大切です。当事務所では、相続手続きや共有解消のご相談を承っております。お悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。