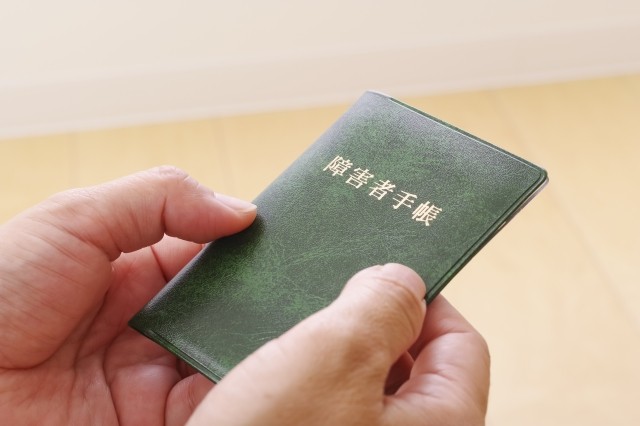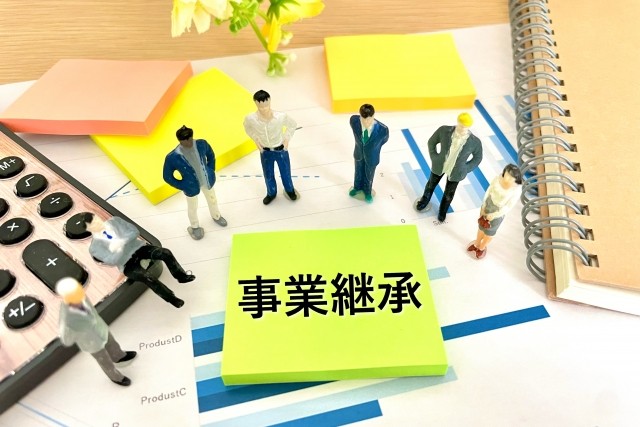~不在者財産管理人・失踪宣告の手続きをわかりやすく解説~
相続が発生したとき、遺産分割協議を進めるにはすべての相続人の参加と合意が必要です。
しかし、相続人の中に連絡が取れない人や長年消息不明の人がいる場合、話し合いを進めることはできません。こうしたケースでは、法律で定められた特別な手続きを踏む必要があります。今回は、相続人が行方不明の場合の具体的な対応方法について解説します。
行方不明者がいると遺産分割は進められない理由
民法第907条により、遺産分割協議は相続人全員で行うことが義務付けられています。
相続人の一人でも欠けたまま行った協議は無効となり、あとからやり直しが必要になります。
そのため、行方不明者がいる場合にはまず「どうやって協議に参加させるか」という法的手当が必要です。
まずやるべきこと ― 行方不明者の所在調査
手続きを進める前に、できる限りの方法で行方不明者の所在を探します。具体的には次のような方法があります。
- 住民票・戸籍の附票をたどって現住所を確認
- 親族や知人への聞き取り
- 勤務先や元住所への問い合わせ
- 郵便物の転送先調査
- SNSやインターネット検索
もし住所が判明すれば、遺産分割協議への参加を依頼できます。
それでも見つからない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」の申立てを行います。
不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは
民法第25条以下の規定に基づき、行方不明者(不在者)の財産を代わりに管理する人を家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、相続手続きにおいて行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加できます。
申立ての流れ
- 申立先:行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立人:利害関係人(他の相続人など)
- 必要書類:
- 申立書
- 行方不明者の戸籍謄本・附票
- 相続関係説明図
- 行方不明であることを示す資料(親族の陳述書など)
- 費用:収入印紙800円+郵便切手(数千円程度)
不在者財産管理人による遺産分割協議
不在者財産管理人が選任されても、すぐに遺産分割に合意できるわけではありません。
遺産分割協議を行うためには、さらに「権限外行為許可」の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
これは、不在者の財産を処分する行為(遺産分割による持分移転など)は、通常の管理行為を超えるためです。
失踪宣告の活用
行方不明の期間が長期にわたる場合は、失踪宣告制度を利用できます。
普通失踪
民法第30条により、7年間生死不明が続くと、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪宣告をすることができ、その人は死亡したものとみなされます。
相続手続きでは、失踪宣告が確定すると、その行方不明者は死亡した扱いとなり、代襲相続や法定相続分の再計算が行われます。
特別失踪(危難失踪)
戦争・船舶事故・震災などの危難に遭遇した場合は、1年間生死不明で失踪宣告が可能です。
実務上の注意点
- 不在者財産管理人は弁護士や司法書士が選ばれることが多いですが、親族の一人が選任されることもあります。
- 管理人は不在者の利益を守る立場なので、他の相続人にとって必ずしも有利な分割内容になるとは限りません。
- 失踪宣告は効力が大きく、もし後に本人が生存していた場合には、相続のやり直しや財産返還が必要になる場合があります。
行方不明者がいる場合の相続手続きフロー(まとめ)
- 行方不明者の所在調査
- 見つからなければ家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立て
- 権限外行為許可を得て遺産分割協議を実施
- 行方不明期間が長期なら失踪宣告の検討
まとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割ができず、相続手続きがストップします。
このような時は、不在者財産管理人や失踪宣告といった制度を活用することが必要です。
ただし、これらの手続きは専門的で時間もかかるため、早めに行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。行方不明の相続人がいて相続が進まない場合は、まずはお気軽にご相談ください。