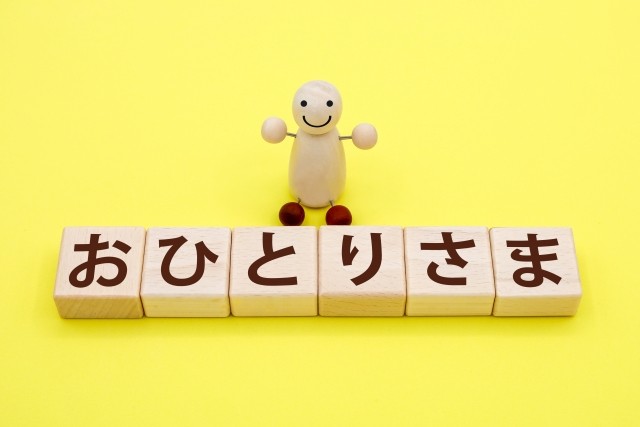「家族が亡くなって、遺産分割をしようとしたら遺言書が見つかった」「兄弟で話し合って分け方を決めようと思ったけど、遺言書の内容と違ってもいいの?」——そんなご相談をよく受けます。
今回は、「遺言書と遺産分割協議のどちらが優先されるのか?」について、法律の基本から注意点まで、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
遺言書とは何か?
遺言書は、故人(被相続人)が「自分が亡くなった後に、財産をどう分けてほしいか」を意思表示した文書です。法的に有効な遺言書がある場合、その内容は原則として尊重され、相続人はその通りに遺産を受け取ることになります。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言:本人が全文を手書きして作成するもの。裁判所での検認が必要。法務局での保管制度もあり。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成。最も確実でトラブルが少ない。
- 秘密証書遺言:あまり使われない形式で、実務上はほぼ見かけません。
遺産分割協議とは何か?
遺産分割協議は、遺言がない場合や、遺言で指定されていない財産について、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名・捺印します。
優先されるのは「遺言書」
結論から言えば、有効な遺言書がある場合は、その内容が最優先されます。
民法第902条では、「遺言による相続分の指定は、法定相続分に優先する」とされています。つまり、被相続人が自分の意思で「誰に何を相続させる」と決めた場合、それを最も重視するということです。
例:遺言書がある場合とない場合の違い
遺言書がある場合:
「長男に自宅を相続させる」と書かれていれば、他の相続人が「平等に分けたい」と希望しても、基本的には遺言の内容に従う必要があります。
遺言書がない場合:
相続人全員で協議して、「長男が自宅を取得し、代わりに預金は次男が取得する」など自由に話し合いができます。
ただし「全員合意」なら遺言と違う分け方も可能
ここで少し複雑になるのが、「相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方もできる」という点です。
民法に反しない限り、遺言の修正は可能
遺言書はあくまで「被相続人の最終意思」ですが、相続人全員が「このように分け直したい」と合意すれば、遺産分割協議で遺言の内容を変更することも可能です。
ただし、その協議には全相続人の同意が必要で、ひとりでも反対すれば変更できません。
遺留分との関係にも注意
遺言によって特定の相続人がまったく財産を受け取れないような内容だった場合でも、その人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、一定の金銭の支払いを求めることができます。
実務で気をつけるべきポイント
遺言書が本当に有効かを確認する
形式不備や、意思能力の問題で無効とされる遺言書もあります。専門家による確認が必要です。
相続人全員の合意が本当に得られているか
「あとで一人だけが反対した」では協議が無効になることも。文書でしっかり証明を残しましょう。
不動産登記など実務手続きとの関係
相続登記の申請時には、遺言書の写しや検認調書、あるいは遺産分割協議書の添付が必要です。状況によって添付書類が異なるため注意が必要です。
まとめ:遺言があればまずはその内容を確認しよう
遺言書と遺産分割協議のどちらが優先されるのか——原則としては遺言書が優先されます。
ただし、相続人員の合意がある場合や、遺留分を侵害しているようなケースでは、遺産分割協議による修正や請求も可能です。被相続人の意思を尊重しつつ、相続人同士が納得できる形で遺産を分けるには、法律知識と調整力の両方が求められます。
「どう分けたらよいかわからない」「遺言書があるけど手続きが不安」——そんなときは、行政書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。当事務所では、遺言書の確認や遺産分割協議書の作成支援を行っています。お気軽にご相談ください。