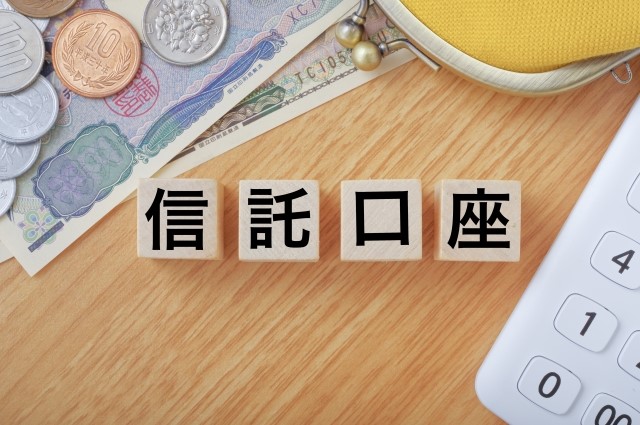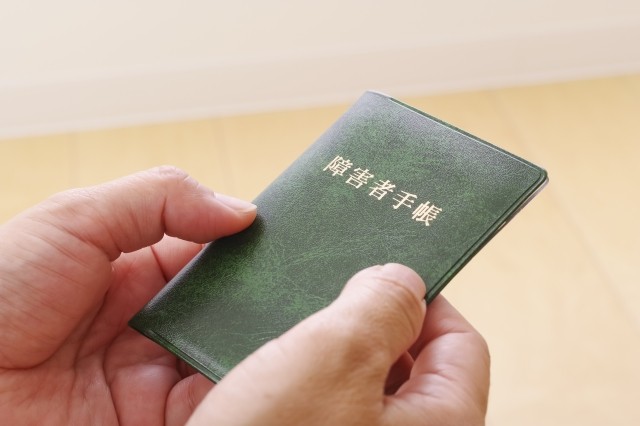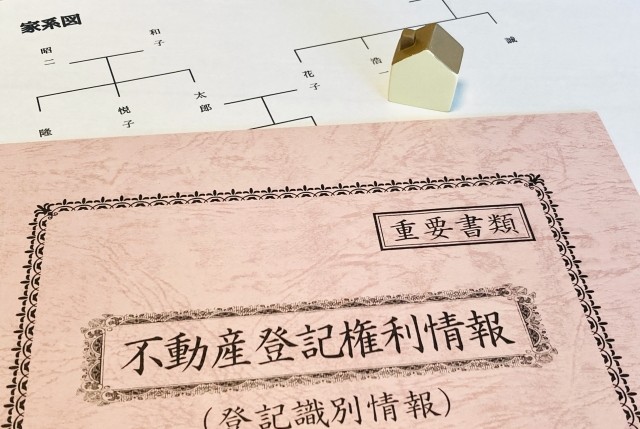
相続が発生すると、多くの手続きが必要になります。預貯金の解約、不動産の名義変更、証券の相続、税務署への申告など、関係機関への提出書類も多岐にわたります。その中で、煩雑になりがちな「戸籍の束」の代わりに使える便利な書類が「法定相続情報一覧図」です。
今回は、この法定相続情報一覧図の基礎知識と、実際の活用方法についてわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、法務局で無料で発行してもらえる公的な書類で、被相続人(亡くなった方)の法定相続人を一覧にした図表のことです。
通常、相続手続きには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍、住民票などが必要になります。これらの書類は複数ページにわたり、提出先ごとにコピーを用意する必要があるため、非常に手間がかかります。
そこで登場したのが、法定相続情報一覧図です。この一覧図を使えば、戸籍一式の代わりに各種相続手続きで利用できるようになります。
作成に必要なもの
法定相続情報一覧図を作成するには、以下のような書類を準備する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続情報一覧図(案)の作成
- 申出書(法務局に提出)
この一覧図(案)は、形式が決まっており、法務局のホームページなどからひな形を入手することが可能です。作成に不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。
活用できる場面
では、具体的に法定相続情報一覧図はどのような場面で活用できるのでしょうか?以下に代表的な場面を紹介します。
銀行での預貯金の相続手続き
銀行口座の解約や名義変更手続きには、通常、戸籍謄本一式が必要です。しかし、法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍謄本の束を何度もコピーして提出する必要がなくなります。
複数の金融機関に相続手続きを行う場合、この一覧図を複数部取得しておけば、大幅に手間を減らすことができます。
不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更手続き(相続登記)でも法定相続情報一覧図は利用可能です。相続登記の際に法務局に提出する書類の一部として使うことができ、戸籍一式を再度提出する必要がありません。
これにより、不動産ごとに登記申請する場合でも、同じ一覧図を使い回すことができ、非常に効率的です。
税務署への相続税申告
相続税申告においても、相続人を証明する書類として一覧図を添付することができます。税理士に依頼している場合でも、この一覧図があれば、関係者との情報共有がしやすくなります。
どこで申請するのか?
法定相続情報一覧図は、被相続人の本籍地や不動産所在地を管轄する法務局で申請できます。郵送申請も可能ですので、遠方の場合でも手続きは可能です。
申請後、数日から1週間程度で「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。この写しは複数枚発行することができます(発行は無料)。
メリットと注意点
メリット
- 無料で取得できる
- 複数の手続きに使い回しができる
- 戸籍の束を毎回提出する手間が省ける
- 相続人全員の証明が1枚にまとまる
注意点
- 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利用できません。
- 法定相続情報証明書の申出後、5年間は何度でも再発行してもらえます。ただし再発行の申出ができるのは「当初の申出人本人のみ」であり、他の相続人などは証明書の再交付をうけられません。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きをスムーズに進めるための非常に有効なツールです。特に、複数の金融機関や不動産が関わる場合には、その利便性は非常に高く、煩雑な戸籍の提出作業を大幅に削減できます。
一方で、必要書類を集めたり、法定相続情報一覧図を作成したりしなければならないので、不安な方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談しながら作成を進めると安心です。