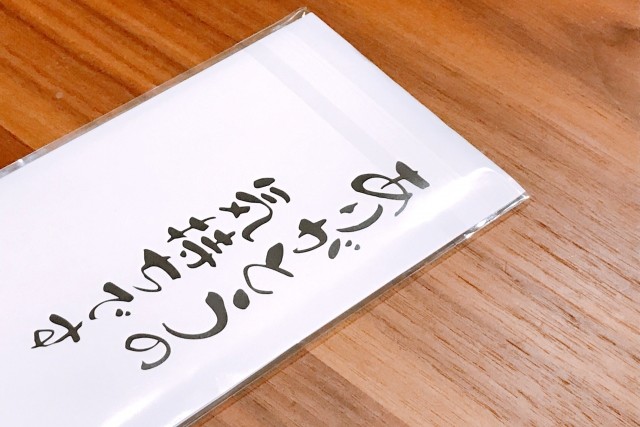「相続した土地を使う予定もないし、管理も負担…」そんな悩みを持つ方が増えています。特に、遠方にある山林や利用価値の乏しい土地を相続した場合、「いっそ手放したい」と思う方も多いのではないでしょうか。
そんな中、2023年4月に施行された相続土地国庫帰属法は、「いらない土地を国に引き取ってもらう」という新たな制度として注目を集めています。しかし、誰でも簡単に土地を国に引き渡せるわけではなく、制度の活用にはいくつかの重要な注意点があります。
この記事では、相続土地国庫帰属法を活用するために知っておくべきポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属法とは?
相続土地国庫帰属法とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地について、一定の条件を満たす場合に限り、国に引き取ってもらえる制度です。手続きを経て法務大臣が承認すれば、土地は国の所有となり、以後の管理責任は不要になります。
制度の目的は、使われていない土地が放置されて社会問題化している現状に対処することです。適切な土地管理がされずに放置された空き地や山林が、防災や景観の面で問題を引き起こすケースもあり、こうした事態の予防策として制度が整備されました。
活用にあたっての主な流れ
- 申請書類の作成・提出(法務局)
- 法務大臣(法務局)による要件審査
- 承認の可否の決定
- 承認後、負担金の納付
- 国への帰属(土地所有権の移転)
注意点① 誰でも利用できるわけではない
この制度を利用できるのは、「相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地を取得した人」に限られます。売買や贈与で取得した土地は対象外となりますので注意しましょう。
また、相続人が複数いる場合は、共有者の全員が共同して申請することで、この制度を利用することができます。
注意点② 引き取ってもらえない土地の要件をチェック
土地を国に引き取ってもらうには、法令で定められた条件をクリアしていることが絶対条件です。
(1) 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
つまり、「問題がなく、整った状態の土地」でなければ、引き取りは難しいというのが現実です。
注意点③ 審査には手間とお金と時間がかかる
申請には、土地の状況を証明する多数の資料が必要です。具体的には、測量図、境界確認書、現地写真、登記簿謄本などのほか、場合によっては専門家の意見書が求められることもあります。
また、土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。なお、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できません。
そして、法務局による審査には数ヶ月以上かかることもあるため、早めの準備が重要です。
注意点④ 負担金が必要
承認された場合、土地1筆ごとに原則として20万円の負担金を納付しなければなりません。これは国が将来的に管理・処分するための費用を一部負担するという趣旨です。
複数の土地を申請する場合、それぞれに負担金が発生しますので、コスト面の見積もりも大切です。
注意点⑤ 不承認になっても土地の所有は継続する
審査の結果、条件を満たさず不承認となった場合は、土地は引き取ってもらえず、自分で管理し続ける必要があります。不承認となる可能性も踏まえ、リスク管理が求められます。
まとめ:制度を活用する前に、専門家への相談を
相続土地国庫帰属制度は、「いらない土地を持ち続ける苦しみ」からの解放につながる可能性がありますが、活用には多数の条件や準備が必要です。
特に以下のような場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします:
- 土地の境界や利用状況があいまい
- 書類の整備が難しい
- 費用対効果を事前に把握したい
土地の処分は一度決めると取り返しがつきません。判断を誤らないためにも、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。