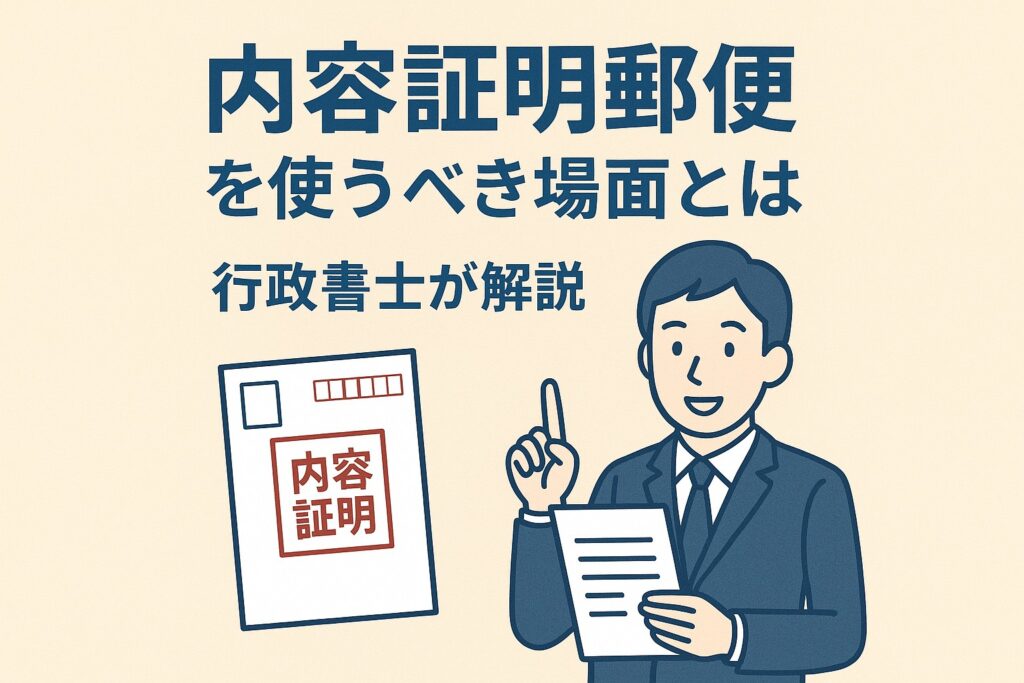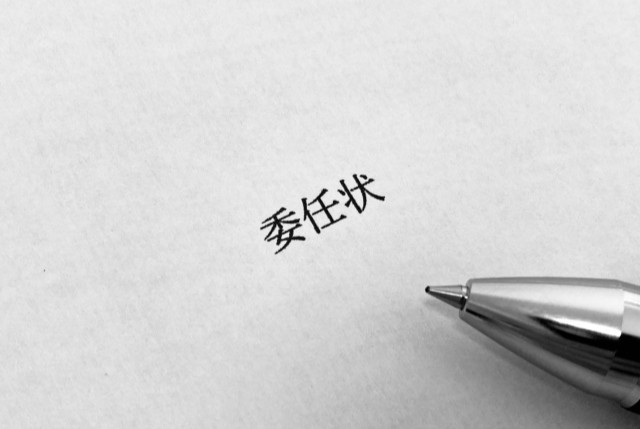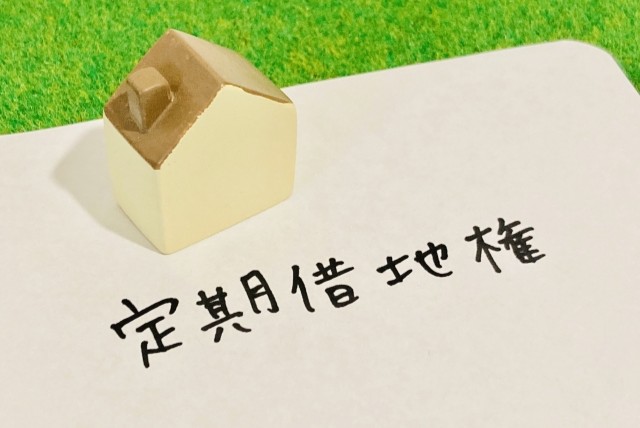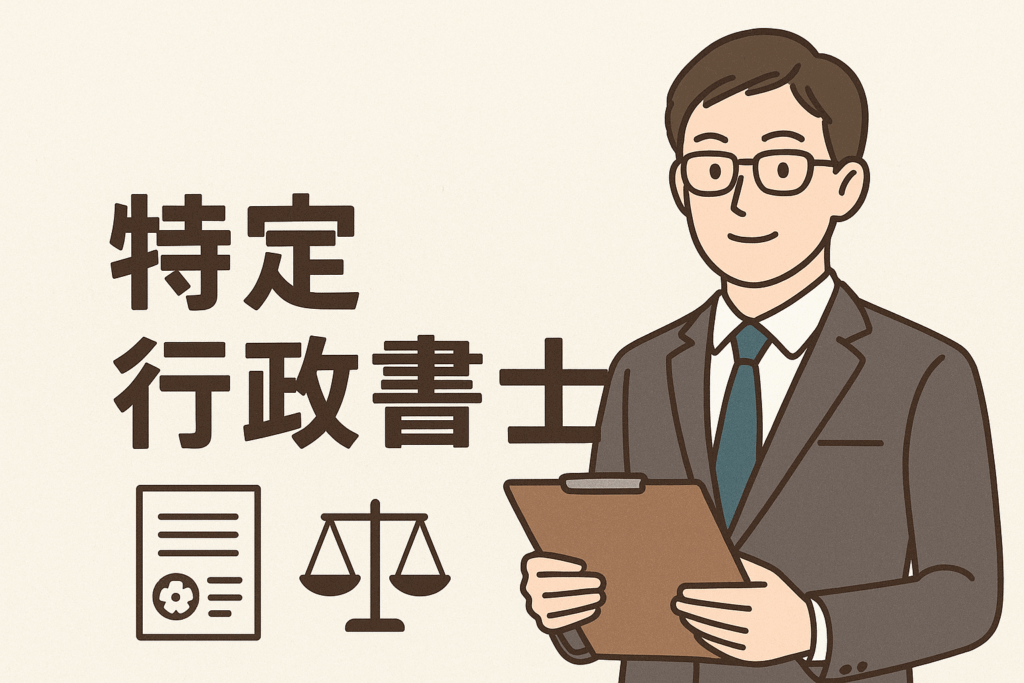「昔貸したお金がまだ返ってこない」「そろそろ時効になるのでは?」——そんな不安を抱える方は多いでしょう。
お金の貸し借りには「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると法的に返還請求ができなくなります。
しかし、時効が成立しても、相手が“時効の援用”をしなければ請求は有効です。
今回は、貸したお金を時効で失わないために、「時効の援用をさせないための方法」を具体的に解説します。
まず知っておきたい「消滅時効」とは
時効の基本
「消滅時効」とは、一定期間、権利を行使しないまま放置していると、その権利が消滅する制度です。
債権の種類によって期間は異なりますが、民法改正(2020年4月施行)以降は、原則として以下の通りです。
| 種類 | 時効期間 |
|---|---|
| 一般の金銭債権(貸金、売掛金など) | 5年(権利行使可能時から) |
| 消費者金融・カードローンなど | 最後の返済期日から5年 |
| 個人間の貸し借り(借用書あり) | 最終弁済期日から5年(旧法では10年) |
時効期間が経過すると、債務者(借主)が「時効を援用します」と主張することで、返済義務がなくなるのです。
したがって、時効完成を防ぐためには、相手に「援用させない」状況を作ることが重要になります。
「時効の援用」とは?
「援用」とは、“時効が成立したことを自ら主張する”ことを意味します。
つまり、債権者が請求しても、「もう時効ですから支払いません」と言われたら、法的には請求が通らなくなります。
ただし、逆に言えば——
👉 債務者が援用しなければ、時効が完成していても請求できるのです。
そのため、「時効が完成する前に行動を起こす」「援用の機会を与えない」ことが、実務上の大きなポイントとなります。
時効を止める、またはリセットする方法
時効完成を防ぐには、「時効の進行を止める」または「リセットする(中断させる)」方法をとります。
これを「時効の完成猶予」と「時効の更新」といいます。
(1)時効の完成猶予:一時的にストップさせる方法
代表的なのが「催告(さいこく)」です。
内容証明郵便などで「返済を求める通知」を送ると、時効の完成が一時的に猶予されます。
- 催告により6か月間、時効の進行が止まる
- ただし、その間に訴訟など「正式な請求手続き」を取らなければ、再び進行する
👉 ポイント
内容証明郵便で催告を行い、その6か月以内に訴訟・支払督促・調停などの法的手続を行うと、時効を確実に止めることができます。
(2)時効の更新:リセットしてゼロからカウント
時効が「更新」されると、時効期間がリセットされ、再び最初からカウントされます。
主な更新事由は次の通りです。
| 更新の方法 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 債務の承認 | 借主が「まだ返していない」と認める | その時点から再スタート |
| 訴訟の提起 | 裁判所に請求を行う | 判決確定後から再スタート |
| 強制執行 | 差押えなどを行う | 執行終了後から再スタート |
特に「債務の承認」は実務上有効です。
例えば、メールやLINEで「もう少し待ってください」「少しずつ返します」と返答があれば、時効が更新されたと認められる可能性があります。
このように、小さなやり取りが大きな法的効果を持つ点を覚えておきましょう。
時効の援用をさせないための具体的対策
① 内容証明郵便で「請求」を明確にする
口頭や電話での催促では証拠が残りません。
内容証明郵便で「いつ・どんな金額を・誰に請求したか」を明確にしておくことが大切です。
これにより、時効完成猶予の効果が生じ、後々の裁判でも有力な証拠になります。
② メール・LINEなどの「承認」を引き出す
相手が「返す意思がある」と認める発言をすれば、時効は更新されます。
やり取りは削除されないように保管しておきましょう。
ただし、相手を追い詰めすぎてトラブルにならないよう、冷静な文面で交渉することが大切です。
③ 訴訟・支払督促・調停などの法的手続きへ
相手が支払いを拒む場合は、時効が完成する前に法的手続をとる必要があります。
訴訟を起こすと、判決確定時点で時効がリセットされ、新たに時効期間が始まります。
④ 債務承認書や和解書を作成する
相手と和解する場合、「分割払いにする」などの合意書を交わすことで、債務承認の証拠となり、時効を更新できます。
行政書士などに依頼して書面化すれば、後日のトラブルを防ぐこともできます。
やってはいけない注意点
- 「口約束だけで待ってあげる」は危険
- 相手の言葉を信じて何年も放置すると、時効成立のリスクが高まります
- 逆に、強引な取立てや脅迫的な言動は法律違反となる恐れがあります
信頼関係を保ちながら、証拠を残しつつ法的に正しい手続をとることが重要です。
まとめ
貸したお金を取り戻せない最大の理由のひとつが「時効の援用」です。
一度援用されてしまえば、法的に請求は難しくなります。
したがって、以下の3つのステップを押さえておきましょう。
- 内容証明郵便で請求して時効を一時停止させる
- 相手から債務承認の言葉を引き出して時効を更新する
- 必要に応じて訴訟や調停で法的手続をとる
時効の問題は「あとでやろう」と思っているうちに取り返しがつかなくなることもあります。
少しでも不安を感じたら、行政書士や弁護士など専門家に早めに相談することをおすすめします。
「貸したお金の時効を援用させない」ためには、感情ではなく、証拠と法的手段で冷静に対応することが大切です。
誠実な対応を続けながら、確実に権利を守りましょう。