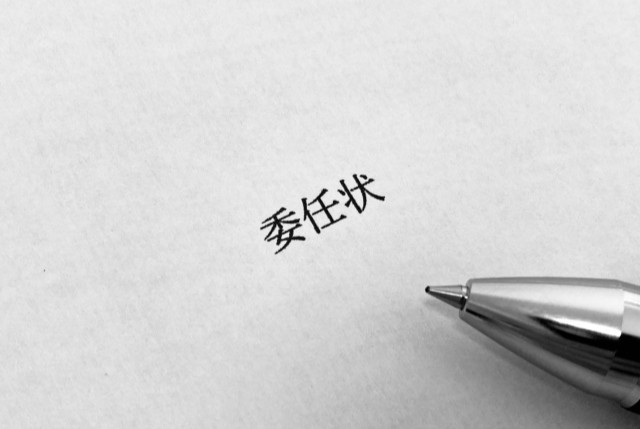調停委員とは何をする人?
「調停委員(ちょうていいいん)」とは、家庭裁判所や簡易裁判所で、当事者同士の話し合いによる解決をサポートする人のことです。
裁判のように「勝ち負け」を決めるのではなく、当事者の意見を聞き取り、合意による円満解決を目指すのが調停の目的です。
たとえば、離婚、相続、養育費、借金問題、近隣トラブルなど、日常生活の中で起こるトラブルの多くは、感情のもつれが原因です。
そうした場面で、調停委員は中立の立場から双方の話を聞き、合意点を見出す“橋渡し役”として活動します。
調停委員の主な仕事内容
調停委員は、裁判官とともに「調停委員会」を構成します。
家庭裁判所では「家事調停委員」、簡易裁判所では「民事調停委員」と呼ばれますが、基本的な役割は同じです。
主な仕事内容は次のとおりです。
- 当事者の話を聞く(傾聴)
双方の言い分を丁寧に聞き取り、感情面も含めて理解に努めます。
時には怒りや悲しみを受け止め、冷静な話し合いに導くことも求められます。 - 争点を整理する
何が本当の問題なのか、どこまでが譲れないのかを整理し、話し合いの方向性を示します。
これにより、感情論から現実的な解決策へと話題を転換します。 - 合意の提案・調整
双方の希望を踏まえて、現実的な解決案を提示します。
たとえば離婚調停なら「親権」「養育費」「財産分与」などを具体的に調整します。 - 調停調書の作成補助
合意に至った場合、内容をまとめて裁判所の調書に反映させます。
この調停調書には、確定判決と同じ効力があるため、法的にも強い効果を持ちます。
家庭裁判所と簡易裁判所での違い
調停委員は、家庭裁判所では「家事事件」(離婚、相続、親子関係など)、
簡易裁判所では「民事事件」(金銭トラブル、近隣紛争など)を扱います。
| 種類 | 主な対象 | 呼称 |
|---|---|---|
| 家事調停 | 離婚、相続、養育費、親子関係など | 家事調停委員 |
| 民事調停 | 借金、家賃、近隣トラブル、金銭問題など | 民事調停委員 |
どちらの場合も、「中立・公平な立場」を守ることが最も大切です。
当事者のどちらかに肩入れするような発言は厳しく避けられています。
調停委員になるには?資格や条件
調停委員は、裁判所法第50条に基づいて最高裁判所が任命します。
ただし、実際には家庭裁判所などからの推薦を受けて選ばれるのが一般的です。
【任命の条件】
- 年齢:おおむね40歳以上70歳未満
- 経験:法律、福祉、教育、医療、地域活動などの分野での社会経験がある人
- 資格:特に必要な国家資格はなし
- 任期:2年(再任可)
つまり、特別な資格がなくても社会経験が豊富な一般市民が活躍できる職です。
弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門職が任命されることもありますが、
地域の元教師、企業経験者、福祉関係者など、さまざまな人が調停委員として活動しています。
報酬や勤務形態
調停委員は非常勤の国家公務員です。
本業を持ちながら、月に数回程度、裁判所に出向いて調停業務を行います。
報酬は1回の出廷につき日額で支払われ、交通費も国家公務員に準じて支給されます。
金額は地域や案件により異なりますが、1日あたり1万円前後が一般的です。
あくまでボランティア精神が重視される仕事といえるでしょう。
調停委員のやりがいと難しさ
● やりがい
- 当事者が話し合いで和解し、笑顔で帰る瞬間に立ち会える
- 社会の“潤滑油”として地域に貢献できる
- 法律知識や人生経験を活かして人の役に立てる
● 難しさ
- 感情的な当事者同士の間に立つ精神的な負担
- 法律だけでなく心理的な配慮も必要
- 根気強く話を聞き、調整するコミュニケーション力が求められる
それでも、「話し合いで問題を解決する」調停の仕組みは、訴訟よりも柔軟で、人間的な側面を大切にできる点が魅力です。
まとめ:調停委員は「話し合いのプロフェッショナル」
調停委員は、裁判官と並んで裁判所の運営を支える重要な存在です。
法律の専門家でなくても、豊かな人生経験と冷静な判断力があれば活躍できる仕事です。
トラブルを「争い」ではなく「対話」で解決へ導く——
そんな調停委員の姿勢は、現代社会が求める“共感と調和”の象徴ともいえます。