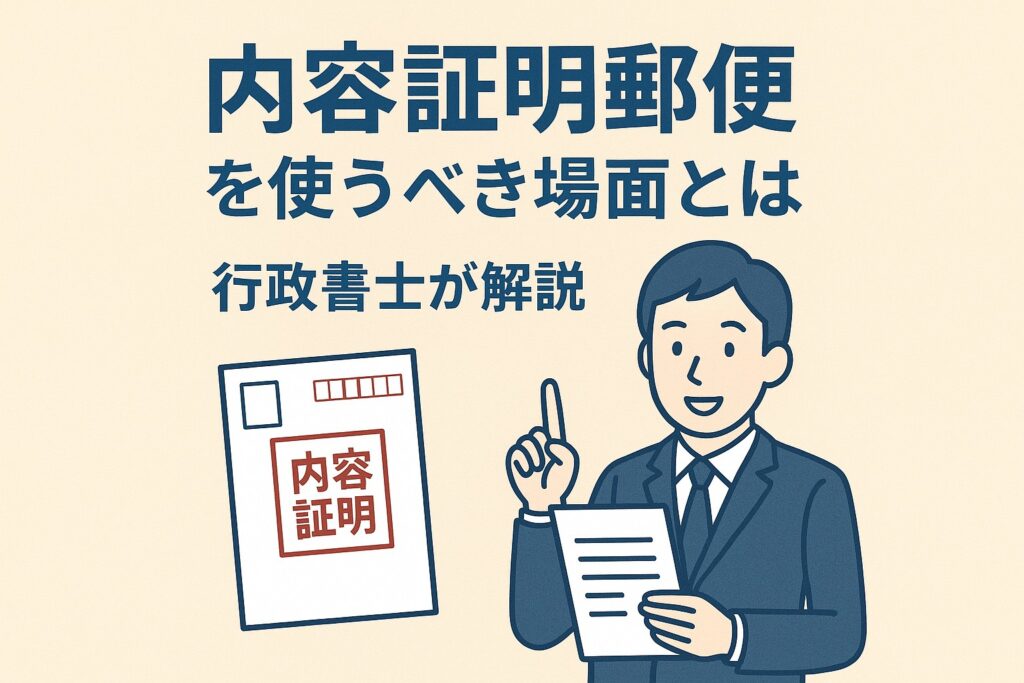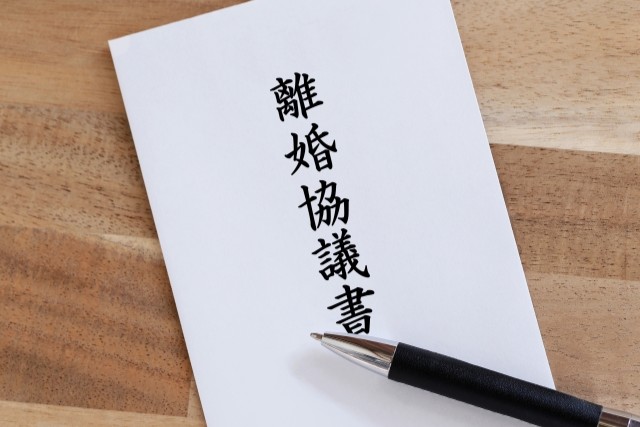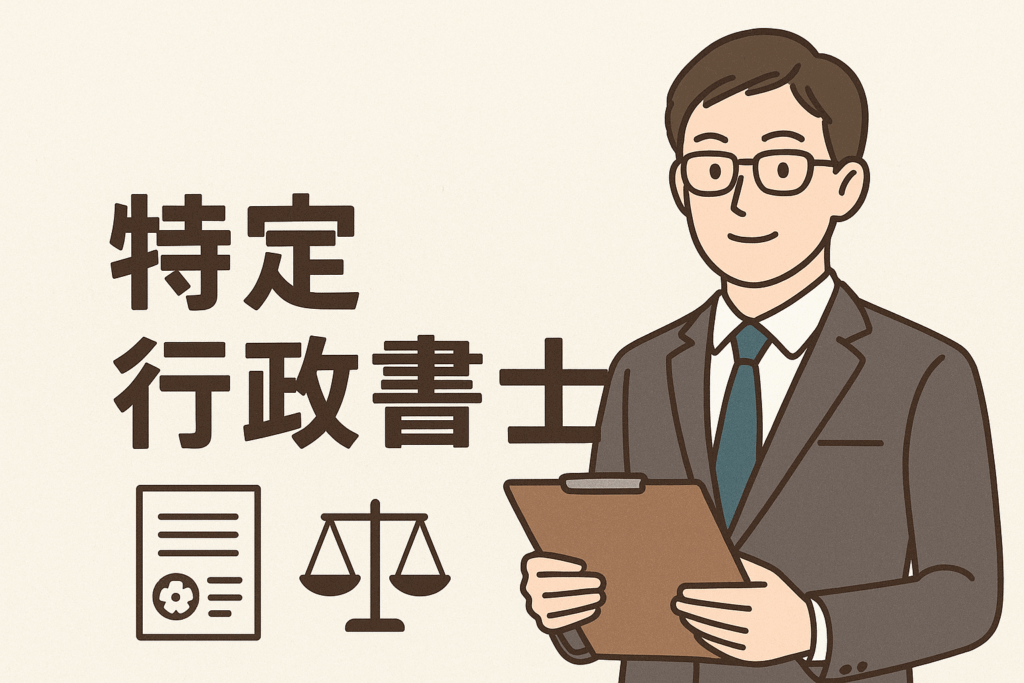高齢化が進む中、「認知症の親の財産管理をどうすればいいのか」「家族が後見人になれるのか」といったご相談が増えています。
この記事では、法定後見人は家族でもなれるのか? という疑問に焦点を当てて、制度の仕組みや注意点をわかりやすく解説します。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、判断能力が不十分になった人を家庭裁判所が保護する仕組みです。
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、自分で契約や財産管理をするのが難しくなった場合に、家庭裁判所が「後見人」を選任し、本人を支援します。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて次の3つの類型があります。
| 類型 | 対象となる状態 | 選任される人 | 本人の行為の効力 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない | 成年後見人 | すべての法律行為を代理できる |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 重要な行為のみ同意・代理 |
| 補助 | 判断能力が一部不十分 | 補助人 | 限定的に同意・代理 |
このうち、一般的に「成年後見制度」と呼ばれるのは、これらをまとめた法定後見制度です。
家族でも法定後見人になれるのか
結論から言うと、家族でも法定後見人に選ばれることは可能です。
ただし、家庭裁判所が最終的に判断するため、必ずしも家族が選任されるとは限りません。
家庭裁判所は、後見人として適任かどうかを次のような観点から総合的に判断します。
【家庭裁判所が重視するポイント】
- 本人との関係(親・子・配偶者など)
- 本人の財産や生活状況
- 家族間の信頼関係やトラブルの有無
- 後見事務を適切に行える能力・時間的余裕
- 利害関係がないか(財産の使い込み、相続争いなど)
そのため、たとえ家族であっても、相続や財産に関して争いがある場合や、過去に金銭トラブルがある場合などには、家庭裁判所が第三者(弁護士や司法書士など)を後見人に選ぶケースがあります。
家族が後見人になるメリット
家族が法定後見人に選ばれると、本人にとって心理的な安心感があり、生活支援の連携もしやすくなります。主なメリットは以下のとおりです。
- 本人の気持ちを理解しやすい
長年一緒に暮らしてきた家族であれば、本人の希望や生活スタイルをよく理解しており、柔軟に対応できます。 - 日常生活の支援がスムーズ
買い物や通院の付き添いなど、身近な生活支援を兼ねて後見業務を行うことができます。 - 費用を抑えられる場合がある
専門職が後見人になる場合、毎月の報酬(2~5万円前後)がかかりますが、家族が後見人になれば基本的に報酬は不要です(ただし裁判所の判断で支給される場合もあります)。
家族が後見人になるデメリット・注意点
一方で、家族が後見人になる場合には注意すべき点もあります。
- 裁判所の監督を受ける
家族であっても、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。
定期的に「後見事務報告書」や「収支明細書」を提出しなければなりません。 - 財産管理の責任が重い
本人の預貯金や不動産を管理するため、使途の記録や領収書の保管が求められます。
不明瞭な支出があると、家庭裁判所から指摘を受けることもあります。 - 家族間トラブルの火種になることも
後見人となった家族が「お金の管理を独占している」と他の親族から不満が出るケースがあります。
透明性を確保し、定期的に家族で情報共有を行うことが大切です。
家族以外が後見人になるケース
家庭裁判所は、本人の利益を最優先に考えるため、次のような場合には専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)を選任します。
- 家族間に意見の対立がある
- 財産が多く、専門的な管理が必要
- 家族が高齢・遠方で後見事務が難しい
- 本人を虐待・搾取した疑いがある
こうした場合、専門職が中立的な立場で財産管理を行い、家族が日常生活の支援を担う「併用型」もあります。
家族が法定後見人になるための流れ
法定後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
手続きの流れは次のとおりです。
- 申立書の作成・提出
申立人が家庭裁判所に提出します。 - 必要書類の提出
・本人の戸籍謄本、診断書(成年後見制度用)
・財産目録・収支予定表
・申立人および候補者の住民票など - 家庭裁判所による審理・面接
家庭裁判所の調査官が、本人や家族に面接を行い、候補者が適任かを判断します。 - 審判・後見開始
裁判所が後見人を選任し、審判が確定すると正式に後見が開始されます。 - 家庭裁判所への定期報告
後見人は、財産の状況や支出内容を定期的に報告します。
まとめ:家族が後見人になるには「信頼と透明性」が鍵
法定後見人は家族でもなることができますが、家庭裁判所の審査を経て適格性が判断されるため、誰でも自動的になれるわけではありません。
選ばれるためには、本人の利益を第一に考え、誠実に財産を管理できる姿勢が重要です。
後見制度は「家族の思い」と「裁判所の公的な監督」が両立する仕組みです。
安心して申立てを進めるためにも、行政書士や司法書士など専門家に相談しながら手続きを行うことをおすすめします。