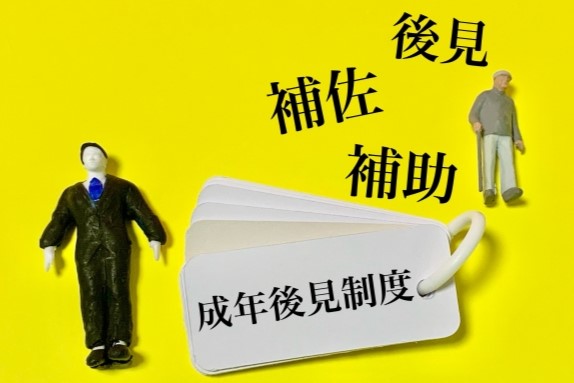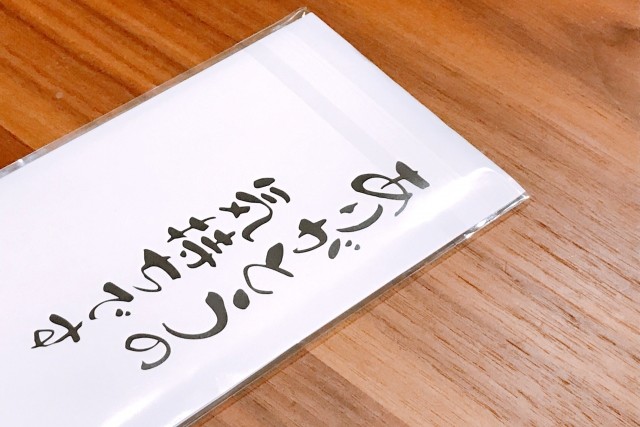
遺言書は、自分が亡くなった後に財産をどのように分けるのかを示す大切な書面です。しかし、財産の分け方だけを機械的に記すだけでは、残された家族が納得できないこともあります。
そのような時に役立つのが「付言(ふげん)」です。付言とは、遺言書の本文とは別に、相続人や大切な人に向けて気持ちやメッセージを記す部分を指します。
今回は、遺言書の付言について、その意義や注意点、実際にどのようなことを書けるのかを解説します。
付言とは何か
付言は、遺言書の中で「遺産分割の効力」を持つわけではありません。つまり、法律上の拘束力はなく、相続人に対して「必ず従わなければならない義務」を生じさせるものではありません。
それでも付言が重要とされるのは、法律だけでは解決できない“人の気持ち”に寄り添う役割を果たすからです。
- 「なぜこのような分け方をしたのか」という理由を説明できる
- 「家族への感謝の言葉」を残せる
- 「将来への願い」を伝えられる
このように付言は、遺言の受け止め方に大きな影響を与えることがあります。
付言を書くメリット
1. 相続トラブルを防ぐ
相続で揉める原因の一つは「納得感の欠如」です。
例えば、長男に自宅を相続させる遺言を残した場合、他の兄弟が「なぜ長男だけなのか」と不満を抱くことがあります。
そこで付言に「長男は長年同居して私の介護をしてくれたため、自宅を託したい」と理由を書けば、他の兄弟も理解しやすくなります。
2. 感謝の気持ちを伝えられる
遺言は財産の分け方を決めるだけではありません。最後に家族へ「ありがとう」を伝える手段でもあります。
付言で「今まで支えてくれてありがとう。家族仲良く過ごしてほしい」と書かれていれば、相続人にとって心の支えになります。
3. 財産以外の想いを残せる
遺言書の本文では「財産の承継」に関することしか効力を持ちません。
しかし付言では「お墓を大切に守ってほしい」「家業を継いでほしい」など、法律に直接関係のない願いを伝えることができます。
付言に書ける内容の具体例
付言は自由に書けますが、よく用いられる内容としては以下のようなものがあります。
- 遺産分割の理由
「長女には教育費を多くかけたので、遺産は次女に多く相続させます。」 - 相続人への感謝やメッセージ
「私の人生を支えてくれたことに心から感謝しています。」 - 相続人同士へのお願い
「どうか兄弟仲良く協力して、家庭を守ってください。」 - 供養や墓守りに関する希望
「○○家の墓を大切に守ってほしい。」 - 特定の人への配慮
「長男の妻には、私の介護を一身に担ってくれたことを感謝します。」
付言を書く際の注意点
付言は法的効力を持たないため、次の点に気をつける必要があります。
- 法律に反する内容は無効
例えば「相続税を払わなくてよい」と書いても、当然ながら効力はありません。 - 遺言の本文と矛盾させない
本文では「長男に自宅を相続させる」としながら、付言に「次男に自宅を大事にしてほしい」と書けば、混乱のもとになります。 - 強制力がないことを理解する
「必ず長男の子に家業を継がせること」という希望を書いても、それに従うかどうかは最終的に家族の判断に委ねられます。
付言の書き方の工夫
- 冒頭に感謝を述べる:「この遺言を書くにあたり、皆さんに感謝の気持ちを伝えたい」
- 理由を明確にする:「○○のためにこのような分け方をしました」
- 柔らかい言葉を選ぶ:命令口調よりもお願いや希望の形にすると受け入れやすくなります。
また、付言をしっかり残したい場合には、公正証書遺言を作成する際に公証人に伝え、正式に遺言書に組み込んでもらうと安心です。
まとめ
付言は法的拘束力を持ちませんが、家族への最後のメッセージとして大きな役割を果たします。
遺産分割の理由を丁寧に書けば争いを防ぐことにつながり、感謝の言葉を残せば遺言が“温かい手紙”として受け止められるでしょう。
遺言書は財産の分配を決めるだけでなく、残された人の心に寄り添うものでもあります。付言を上手に活用し、財産だけでなく「想い」も次の世代へ伝えていきましょう。
📌 ポイント
- 付言は法律上の効力を持たないが、家族に想いを伝える重要な役割を担う。
- 相続トラブル防止や感謝の伝達に効果的。
- 本文と矛盾しないように注意することが大切。