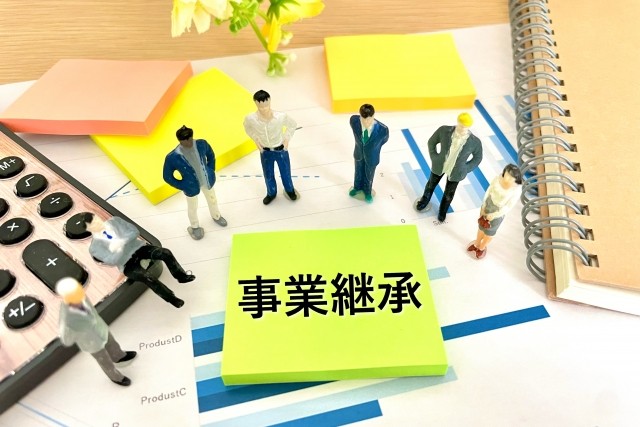近年、相続や資産承継の方法として「民事信託(家族信託)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。一方で「商事信託」という用語もあり、両者はどう違うのか混乱される方も少なくありません。
本記事では、民事信託(家族信託)と商事信託の違いを整理し、それぞれの特徴や利用場面についてわかりやすく解説します。
信託とは何か
まずは基本から確認しておきましょう。
「信託」とは、委託者(財産を持つ人)が受託者(信頼できる人や法人)に財産を託し、その財産を特定の目的のために管理・処分してもらい、その利益を受益者が受け取る仕組みをいいます。
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:財産を託され管理・処分する人
- 受益者:財産の利益を受ける人
この三者の関係によって信託は成り立っています。
民事信託(家族信託)とは
定義
「民事信託」とは、営利を目的とせず、主に家族や親族の間で行われる信託を指します。特に相続や認知症対策として利用されるケースが多いため「家族信託」と呼ばれることもあります。
目的
民事信託の最大の目的は、財産を柔軟に承継させることです。
例えば、
- 認知症になった場合の財産管理
- 二世代、三世代先まで財産の承継先を指定する
- 遺言書では難しい柔軟な財産分配
といった場面で活用されます。
特徴
- 非営利:受託者(多くは家族)が報酬を得ることを目的としていない
- 自由度が高い:民法や信託法の範囲でオーダーメイドの設計が可能
- 相続対策に有効:遺言や成年後見制度では対応できない柔軟な仕組み
商事信託とは
定義
「商事信託」とは、信託業法に基づき、営利を目的として信託を業として行うものをいいます。信託銀行や信託会社などの専門業者が取り扱います。
目的
商事信託の目的は、顧客から信託財産を受託し、プロの管理運用によって利益を生み出すことです。
例えば、
- 投資信託
- 年金信託
- 不動産管理信託
などが典型です。
特徴
- 営利目的:信託会社・信託銀行などが業務として行う
- 専門性の高さ:金融商品や不動産運用などプロが管理
- 信託業法の規制:登録・許可が必要であり、個人は原則として行えない
民事信託(家族信託)と商事信託の違い
ここで両者の違いを整理してみましょう。
| 項目 | 民事信託(家族信託) | 商事信託 |
|---|---|---|
| 主な担い手 | 家族や親族など個人 | 信託銀行・信託会社 |
| 目的 | 財産管理・承継、相続対策 | 投資・資産運用など営利 |
| 利益 | 原則無報酬(非営利) | 手数料や運用益を目的とする |
| 規制 | 信託法 | 信託法+信託業法 |
| 主な利用場面 | 認知症対策、相続承継 | 投資信託、不動産信託、年金信託 |
利用場面の違い
民事信託(家族信託)の利用場面
- 親が高齢で財産管理が心配
- 障がいのある子の生活を長期的に支援したい
- 二次相続、三次相続まで承継先を決めておきたい
商事信託の利用場面
- 資産運用をプロに任せたい
- 退職金を年金として受け取りたい
- 不動産を信託して収益管理をしたい
メリット・デメリット
民事信託(家族信託)
- メリット
- 自由度が高く、相続対策に柔軟
- 成年後見制度の代替として利用可能
- デメリット
- 専門家の設計が必要で複雑になりやすい
- 信託銀行のように高度な運用はできない
商事信託
- メリット
- プロによる安全かつ効率的な財産管理
- 多様な金融商品への投資が可能
- デメリット
- 手数料やコストが発生する
- 個人のきめ細やかな希望には対応しにくい
まとめ
民事信託(家族信託)と商事信託は、同じ「信託」という仕組みを利用しながらも、その目的や担い手、利用場面は大きく異なります。
- 民事信託(家族信託)は、家族間で財産管理や相続をスムーズに行うための非営利の仕組み。
- 商事信託は、金融機関が営利を目的に資産運用や管理を行う仕組み。
ご自身やご家族の状況に応じて、どちらを活用するのが適しているかを考えることが大切です。相続や財産管理に不安を感じたら、行政書士や専門家へ早めに相談することをおすすめします。