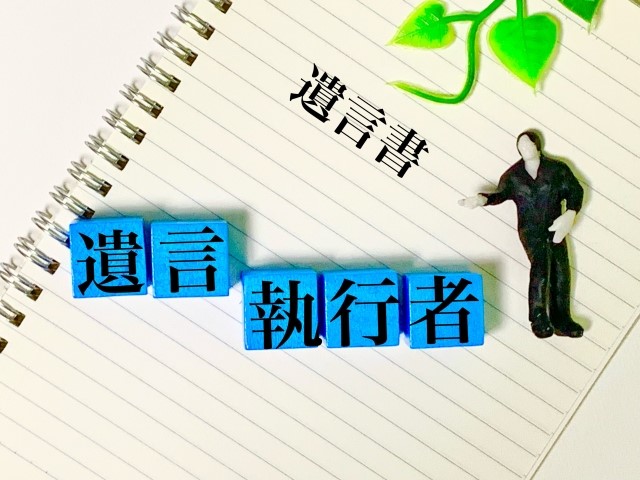相続の場面では、法定相続人が集まって「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決めるのが一般的です。ところが、その中に認知症を患っている方がいる場合、協議は思うように進みません。判断能力が十分でないと、協議内容に同意して署名捺印すること自体が無効となる可能性があるからです。
今回は、法定相続人に認知症の方がいる場合の注意点と対応方法について解説します。
認知症の相続人がいると遺産分割協議はできない?
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。たとえ一人でも欠けていると協議は無効になります。
認知症の方が相続人に含まれる場合、以下のような問題が起こり得ます。
- 判断能力が低下しており、協議内容を理解できない
- 書類に署名・捺印をしても、その意思表示が有効かどうか疑問となる
- 他の相続人が不利にならないか、適正に判断できない
このため、認知症の方がいる場合は、成年後見制度などを利用し、法的に有効な手続きを整える必要があります。
成年後見制度の利用が必要
成年後見制度とは?
家庭裁判所に申立てを行い、認知症などで判断能力が十分でない方に代わって法律行為を行う「後見人」を選任してもらう制度です。
- 成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
- 後見人は本人の利益を最優先に考えて協議を進める義務があります。
- 後見人には、親族が就任する場合もあれば、弁護士や司法書士など専門職が選任される場合もあります。
成年後見制度を利用する流れ
- 家庭裁判所に申立てを行う
- 医師の診断書を提出
- 裁判所が審理を行い、成年後見人を選任
- 後見人が就任後、遺産分割協議に参加
申立てから選任までには、通常2〜3か月程度かかります。相続手続きを急ぎたい場合でも、まずは後見人選任が必要になる点に注意が必要です。
成年後見人がいる場合の遺産分割協議
成年後見人が就任すると、その人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。
ただし、注意点があります。
- 後見人は、本人の財産を「減らす」ような合意はできません。
例:本来2分の1をもらえるはずなのに「ゼロでいい」といった協議はできない - 不公平な内容にならないよう、必要に応じて家庭裁判所に「遺産分割許可」の申立てが必要になる
このように、成年後見人を通すことで公平性と適法性が担保されるのです。
任意後見制度を検討するのも有効
認知症が進む前であれば、本人が元気なうちに「任意後見契約」を結んでおくことも可能です。
- 本人が信頼できる人を後見人としてあらかじめ契約
- 将来、判断能力が低下したときに効力が発生
- 財産管理や相続手続きもスムーズに進めやすい
ただし注意点!
任意後見契約を結んでいても、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します。
監督人がいない状態では、任意後見受任者はまだ「代理権」を持っていないため、遺産分割協議には参加できません。
つまり、任意後見の場合も、必ず家庭裁判所で任意後見監督人が選任される必要があるという点を押さえておきましょう。
相続手続きでよくあるトラブル事例
- 成年後見人を立てずに協議を進めたケース
→ 後日、無効とされ、やり直しになった。 - 親族間で後見人の選任をめぐり対立したケース
→ 家庭裁判所が弁護士を選任し、費用負担が大きくなった。 - 相続税の申告期限に間に合わなかったケース
→ 後見人選任に時間がかかり、申告期限の10か月を過ぎて加算税が課された。
このように、早めの対応がトラブル防止のカギとなります。
認知症の相続人がいる場合の対応まとめ
- 相続人に認知症の方がいると、そのままでは遺産分割協議ができない
- 成年後見制度を利用して、後見人を選任する必要がある
- 任意後見契約をしていても、監督人が選任されなければ効力は発生しない
- 手続きには時間がかかるため、早めの準備が重要
行政書士にできるサポート
行政書士は、
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人調査や戸籍収集
- 成年後見制度の申立書類作成
といった面でサポートできます。
認知症の方が相続人にいる場合、相続手続きは一筋縄ではいきません。トラブルを避け、円滑に進めるためには、早めに専門家に相談することが安心につながります。
当事務所では、相続や成年後見に関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。