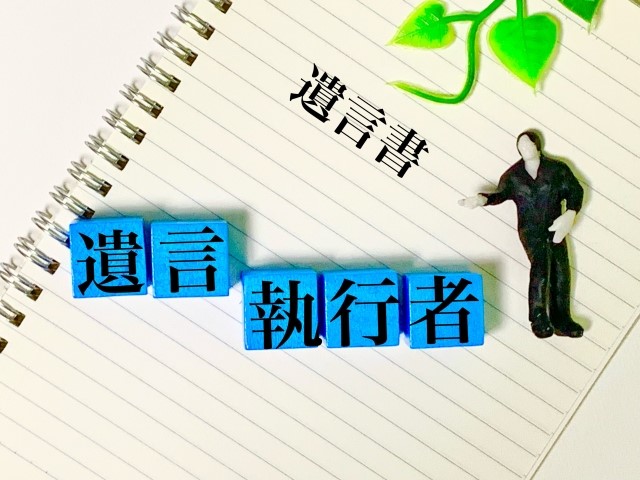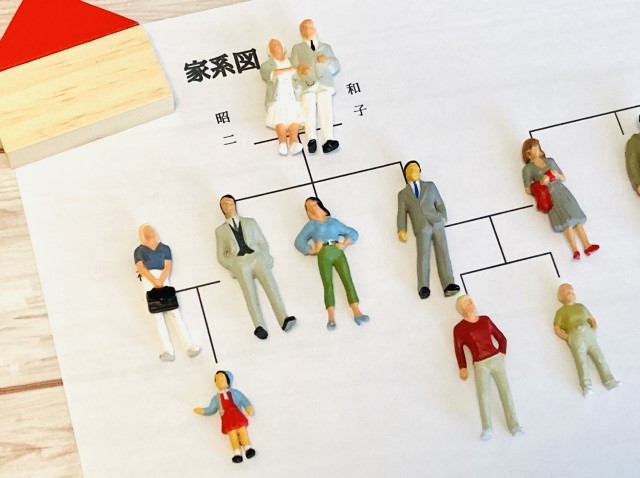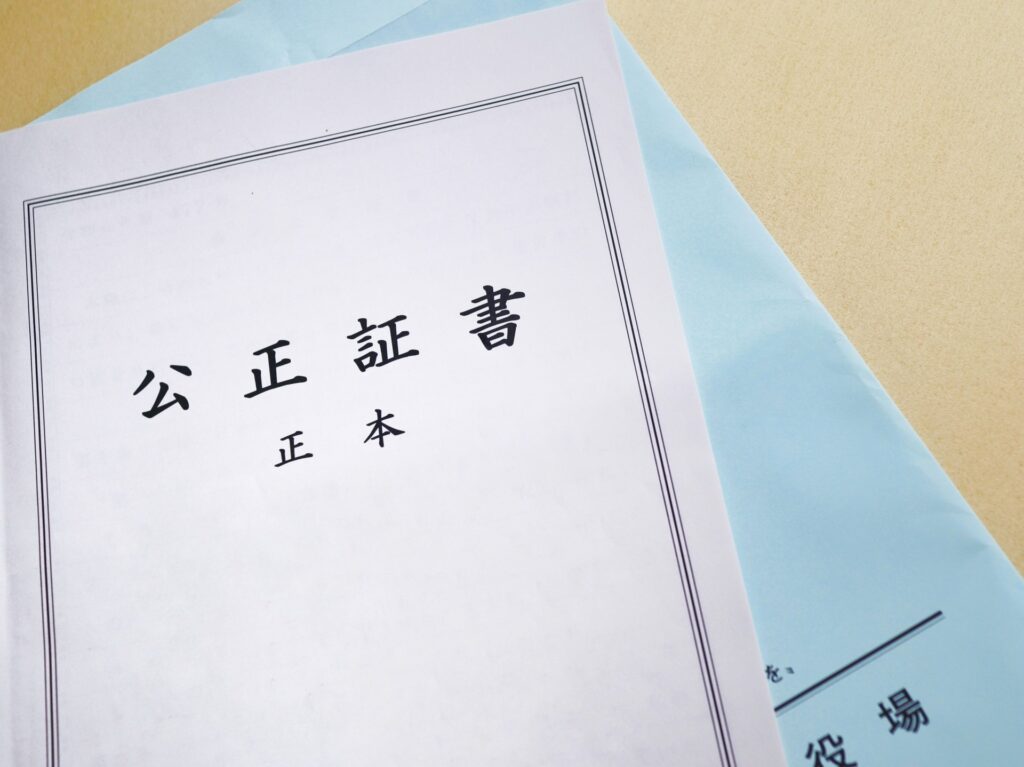遺言書を作成する際、「~を相続させる」と「~を遺贈する」という表現を使い分けることが重要です。これらはどちらも財産の承継を意味しますが、法律上の効果が異なります。場合によっては、指定された特定財産だけを辞退したいのに、そのほかの遺産を含めてすべて相続放棄しなければならなくなるなど、注意が必要です。本記事では、それぞれの違いについて詳しく解説し、どのように使い分けるべきかを説明します。
「~を相続させる」とは?
「~を相続させる」とは、被相続人(故人)が相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に財産を承継させる場合に使用する文言です。法定相続人以外には使うことができません。これは、遺言による相続の指定であり、法的には「遺産の承継」に該当します。
メリット:
- 登記や引き渡し手続きが簡略化:不動産を「相続させる」とした場合、遺言執行者は遺産分割協議を経ずに単独で所有権移転登記を申請できる。
デメリット:
- 相続放棄が必要:指定された特定財産を相続したくない場合は、その他の遺産を含めてすべて相続放棄をしなければならない。指定された特定財産を受け入れるか、その他の遺産を含めて相続放棄するかの選択に迫られる。
【使用例】
- 「私の所有する群馬県高崎市の土地(登記番号1234-56)を長男○○に相続させる。」
- 「私の預貯金(○○銀行○○支店、口座番号1234567)を配偶者○○に相続させる。」
「~を遺贈する」とは?
「~を遺贈する」とは、被相続人が相続人または相続人以外の第三者(相続人でない親族や知人、慈善団体など)に財産を譲る場合に使用する文言です。遺贈は「遺言による贈与」にあたり、遺言によって財産を特定の人に与えることができます。
メリット:
- 相続人以外の人にも財産を渡すことができる。
- 指定された特定財産の遺贈を辞退する場合でも、その他の遺産を相続することができる。
デメリット:
- 登記や名義変更の手続きが煩雑:不動産を遺贈する場合、受遺者(遺贈を受ける人)は遺言執行者や相続人などの遺贈義務者と共同で登記手続きを行わなければならない。
- 第三者に対抗するには登記が必要:遺贈の場合、第三者が遺贈の内容を確認する手段がないため、第三者に対抗するためには登記が必要とされている。
【使用例】
- 「私の所有する東京都新宿区のマンションを、友人○○に遺贈する。」
- 「私の遺産の半分を、社会福祉法人○○に包括遺贈する。」
まとめ
「~を相続させる」と「~を遺贈する」は似たような表現ですが、法的な意味や手続きに違いがあります。相続人に特定の財産を確実に渡したい場合は「相続させる」、相続人が特定の財産を辞退するかもしれない場合や、相続人以外に渡したい場合は「遺贈する」を使うのが適切です。
遺言を作成する際には、専門家(行政書士や弁護士など)に相談し、適切な表現を選ぶことが重要です。誤った文言を使うと、相続手続きが複雑になったり、意図した通りに財産が引き継がれなかったりする可能性があるため、注意が必要です。遺言の作成に不安がある場合は、専門家に相談し、円滑な相続・遺贈ができるように準備しましょう。