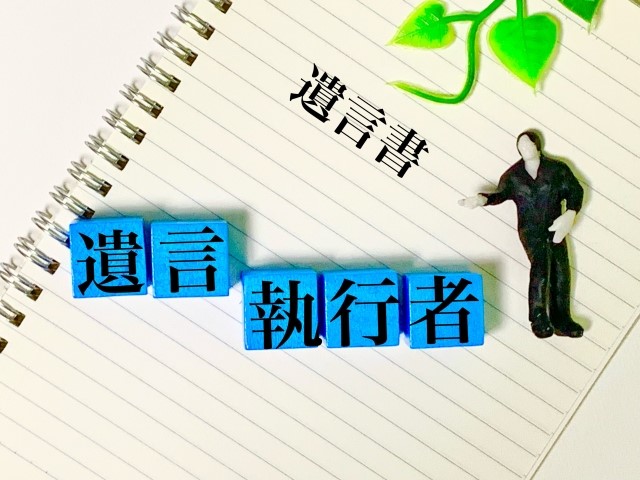日本の中小企業において、事業承継は重要な課題の一つです。経営者の高齢化が進む中、円滑な事業承継ができずに廃業を選ばざるを得ないケースも少なくありません。そんな中、近年注目されているのが「家族信託」を活用した事業承継の方法です。本記事では、事業承継の課題と家族信託の活用方法について解説します。
事業承継の課題
後継者の不在
多くの中小企業では、後継者が決まらないことが大きな問題となっています。特に子どもが事業を継ぎたがらないケースや、適任者がいない場合、事業の存続自体が危ぶまれます。
相続争いのリスク
事業資産が相続財産に含まれるため、相続人同士で争いが生じる可能性があります。例えば、経営に関与していない相続人が財産分与を求めることで、会社経営が不安定になることがあります。
経営の空白期間
経営者が突然の病気や事故で意思決定できなくなると、会社の運営に大きな支障をきたします。特に中小企業では、社長が全ての決定を担っているケースが多く、リスク管理が十分に行われていない場合が少なくありません。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を信頼できる家族や第三者に託し、管理・運用を任せる制度です。通常の相続とは異なり、財産の管理を生前から計画的に行うことができます。特に事業承継においては、次のようなメリットがあります。
事業承継における家族信託の活用方法
事業用資産の管理と運用
家族信託を活用することで、事業用資産(不動産や株式など)を後継者に円滑に引き継ぐことが可能になります。たとえば、信託契約を通じて、経営権を特定の後継者に確実に移行できるように設定できます。
認知症対策
経営者が認知症を発症すると、銀行取引や契約行為ができなくなるリスクがあります。家族信託を活用すれば、信頼できる家族に財産管理を託し、経営をスムーズに継続することができます。
相続トラブルの回避
家族信託では、あらかじめ財産の分配や管理方法を決めておくことができるため、相続時の争いを未然に防ぐことが可能です。例えば、事業に関与する子どもには経営権を与え、関与しない子どもには別の資産を分配するといった柔軟な対策が取れます。
柔軟な財産承継
家族信託では、受益者(財産を実質的に享受する人)を設定できるため、たとえば「経営者が生存中は自らが受益者となり、死亡後は後継者が受益者となる」といった形で、段階的な事業承継を実現できます。
家族信託の手続き
家族信託を活用するには、以下の手順を踏む必要があります。
- 信託契約の作成 – どの財産を信託するのか、管理者(受託者)は誰にするのかを決定します。
- 公証役場での契約締結 – 信託契約は公証役場で公正証書として作成することが推奨されます。
- 信託財産の登記 – 事業用不動産や会社の株式を信託する場合、登記や名義変更の手続きを行います。
- 運用開始 – 受託者が信託契約に基づいて財産を管理・運用します。
まとめ
事業承継は、多くの中小企業経営者にとって避けて通れない課題です。家族信託を活用すれば、円滑な事業承継を実現し、相続トラブルを回避しながら、会社の存続を確実にすることができます。
ただし、家族信託には専門的な知識が必要なため、実施を検討する際は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。事業承継の問題を未然に防ぎ、次世代にしっかりと事業を引き継ぐために、ぜひ家族信託の活用を検討してみてください。